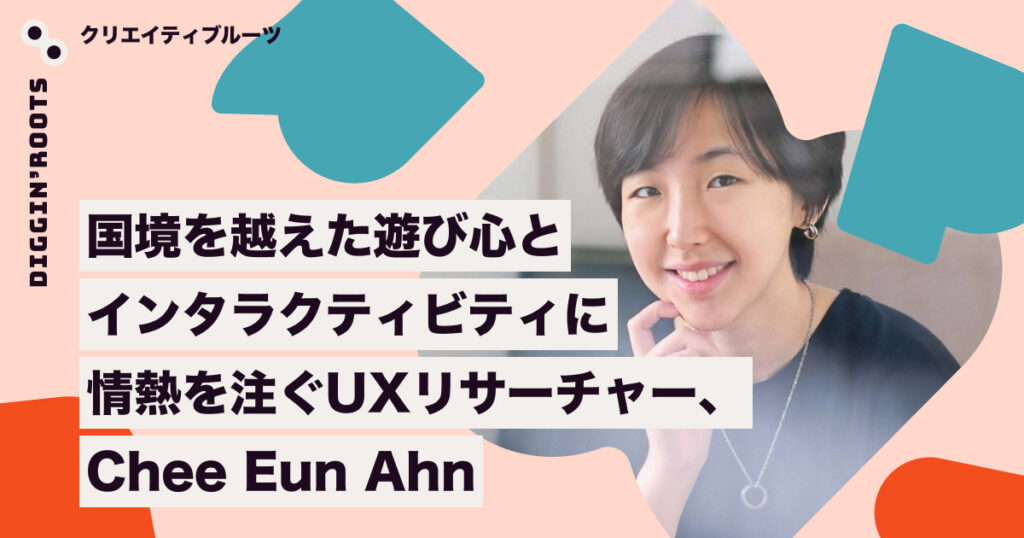日本の歴史、伝統や文化から多様な視点を見出すUXディレクター、川崎沙織
人にはそれぞれ思想や世界観があり、その元となるインスピレーションやルーツがある。一見ひとつひとつはランダムな点に見えても、それらは線となって今の活動のなにかの糧になっているはずだ。だから、さまざまな人がさまざまなデザインをするのだ。
・・・
今回は日本の歴史、伝統や文化的活動から多様な視点を見出し、その発見をUXデザインにつなげているフリーランスUXディレクター川崎沙織さんのクリエイティブルーツを探ります。

複数のデザイン会社を経て独立。現在ではフリーランスのディレクター兼デザイナーとして、要件整理やユーザー調査から、チームの育成まで幅広く支援。サービスデザインをRPGになぞらえてトレーニングするコミュニティ、サービスデザインクエストの代表を務める。
1. 仕事やものづくりへの哲学、こだわりはなんですか?
常に大切にしたいことは、「事実を基に前提を作ること」と「人を動かす行動をすること」です。

チームでひとつのものを作るにあたって、主観ではなく客観的な事実を基に作ったのかどうかが、スムーズに物事を運ぶ上でものすごく大事だなと思いました。ユーザー調査を行って、目で見た、耳で聞いたことを前提に仮説を作るのは絶対に死守しようと決めています。それを抜かして作業をすると巻き戻りが発生するので、最初にセグメントを切って一次情報を取る。また、チームメンバーを支援する上でも、最初からワークショップや面談をせず、ひたすら観察をしてメンバーの状況や状態を目で確認してから問題解決にあたるようにしています。
そして、チームの問題解決においては「信頼」が欠かせません。まずは自分に相談してもらえるように、そして問題解決の行動の輪が広がっていくようにするために、「自分の行動の結果から、周りの行動を引き出すには?」を常に考えています。まだまだ未熟で、自分のキャパシティや相手との関係性にもよるので徹底するのはとても難しいですが、できうる限り意識して動いています。
2. あなたが仕事をはかどらせるためにやっていることや、愛用しているものがあれば教えてください。
未知のものを経験して学習していく感覚を思い出すために、未体験のことに積極的に踏み出すようにしています。最近、「音楽演奏」を始めました。

音楽演奏には憧れてはいたのですが、今まで全くやったことがないことでした。挑戦してみると難しいし、人前で弾くのは恥ずかしいし、とても心地悪く感じたんです。ですが、演奏していると周りの人が合わせてくれてひとつの音楽になっていく快感や、楽器を通して人とつながる楽しさに感動しました。心地悪さを乗り越えて、未知のことにトライする感覚を思い出させてくれる貴重な体験だと思っています。
初学のものが生活の中にあることは、自分の成長にとって重要だと感じます。今は十分に仕事をいただいていますが、10年後も同じように居場所を保てているかはわかりません。新しい経験は「今の自分はできている気になっていないか?」という問いかけにつながっています。今できる範囲のことだけを磨いていくのではなく、できないことにも侵食していかなければ、と思っています。ただ、あまり義務感にとらわれず「楽しめること」をやっています。
3. あなたが影響を受けた人は誰ですか?
仕事の側面では、「情報デザイン」の概念を初めて作った、リチャード・ワーマン氏がダントツですね。彼の著書『情報選択の時代』という本を大事に読んでいます。

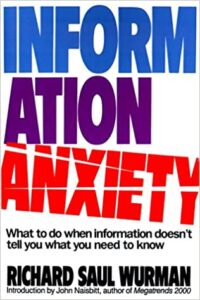
(出典 : Amazon.com)
この本そのものの情報デザインもとても優れていて、どこからでも読み始められるようになっています。読む度に発見があるんです。
最初に読んだのは、25〜26歳くらいの時でした。この本を読んで、「相手の心情に沿って伝える方法を覚えないと、人生損するんだな」と気付かされました。仕事に限った話ではないですよね。家族や友達との喧嘩にも当てはまることだと思います。
この本ではリチャード・ワーマン氏はそのような「誰にでも起こり得る話」を通じて、「経験と情報が結び付かないと、基本的に意味が無い」ということを述べています。実体験や調査からの背景があってこその情報デザインなので、それまでの文脈が大事だと教えてくれました。
また、「データと情報は違う」ということも学びのひとつでした。今の社会はデータの収集がたやすくなって大量のデータがありますが、それを「意味のある情報」として扱えていないと感じることが多々あります。必要な情報をデータから認識しやすいビジュアルにデザインする力が豊かな体験を作るのに重要であると、ハッとさせられました。
4. あなたのデザインや考え方のルーツとなったコンテンツはありますか?

高校生のころ、親戚がいる京都に何度も行く機会があって、その時に衝撃を受けた出来事がありました。お寺の日本庭園で庭師の方が作業しているあたりに「留め石」が置いてあったんです。留め石というのは、庭の手入れをしてる時に人が入って来ないように目印として置いておく紐が結ばれた小さい石です。それを見た時「広い空間に小さい留め石が置いてあるだけで、『この先進んではいけない』とわかるのすごい!」と、衝撃を受けました。

庭のデザインが考え抜かれているからこそ、ちょっとの違和感で人が止まるんですよね。人の行動を促し、どう見てもらいたいのかを徹底して考えられた庭園を作ってるんだろうなと気づいたときに「日本すごい!」と感銘を受けました。西洋の庭園にこれが置いてあっても誰も気にせず、石を避けて通ってしまうと思います。
調和を大切にしながら、最小限の表現で味わい深い体験を残す文化観がかっこいいと思います。それが日本らしいデザインなんだな、と改めて感じました。「相手が見えているもの」にフォーカスを当てないと思いつかないことなので、UXデザインのお手本だなと感じます。
5. 10代の頃に好きだったものやハマっていたことはなんですか?

歴史小説や歴史系のコンテンツをよく見ていました。当時流行っていた『るろうに剣心』という漫画がきっかけです。最初はバトル漫画として読んでいたんですが、そのうちその時代に関する小説を読みたくなりました。作中で登場した歴史上の人物について、「どんな人なのかな」とサブストーリー感覚で読んでいたんです。
ストーリーの中で政治に触れている部分もあり、より詳しく理解したくて他の文献も読んでみたらそれが想像以上に面白かったので、そこからたくさんの歴史の本を読みました。それをきっかけに、日本に住んでいた人たちの生活はどう移り変わってきたのかを調べるのが好きになったんです。
今の日本の例えば、京都と東京の道路の設計の違いや、金融サービスの成り立ちなど、「今の生活の感覚や常識は、なんでこうなっているんだろう?」を知るのが特に好きです。歴史を知ると自分達がなぜこういう状況にいるのかが理解でき、「歴史の上に自分が生きてるんだな」と実感してから世界が面白くなったので、10代のころは日本史に夢中でした。
6. 最近「いいデザインだな〜」と思ったサービスやWebサイトはありますか?

Oisixのミールキットです。ECやスーパーで買える、献立に合わせた食材と調味料が入ったキットです。何年か前に初めて使ってから、いまもよくお世話になっています。
食産業では「野菜を食べてもらえない」という課題を抱えているそうなのですが、Oisixではもう一歩踏み込んで「本当は野菜は食べているが、野菜を買っていないのでは?」と問いを立て直し、「野菜を買わない理由」を解消する商品を開発しているという話を聞きました。
ミールキットなら自分では挑戦しにくい野菜を取り入れて、栄養も考えられたおいしい料理ができます。自分でも使ってみて、旬の野菜・食べたことのない野菜を食べるようになったので、とても納得感がありました。
視点を変えて問い直し、本当に役立つものを作って多くの人に使われているというのは、本当にすごいことだと思います。問題に向き合うとき、常に柔軟であるべきだと考えさせられました。
・・・
関連リンク
DESIGN STUDIO EITEL:川崎さんの活動が紹介されています