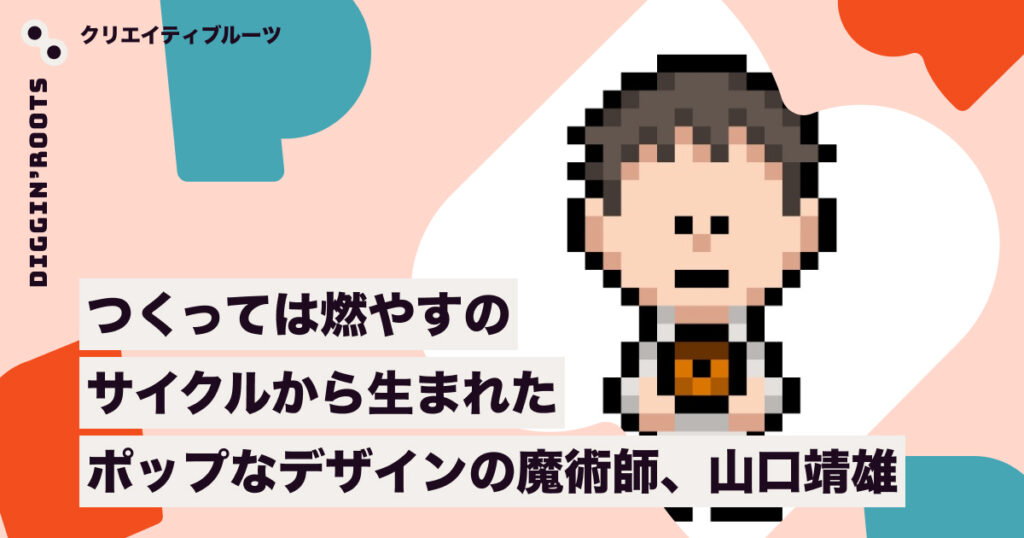デジタルもリアルもたくましく生き抜くサバイバル系デザイナー、河西紀明
人にはそれぞれ思想や世界観があり、その元となるインスピレーションやルーツがある。一見ひとつひとつはランダムな点に見えても、それらは線となって今の活動のなにかの糧になっているはずだ。だから、さまざまな人がさまざまなデザインをするのだ。
今回は自然をサバイブするワイルドブッシュクラフト系デザイナー河西さんのクリエイティブルーツを探ります。
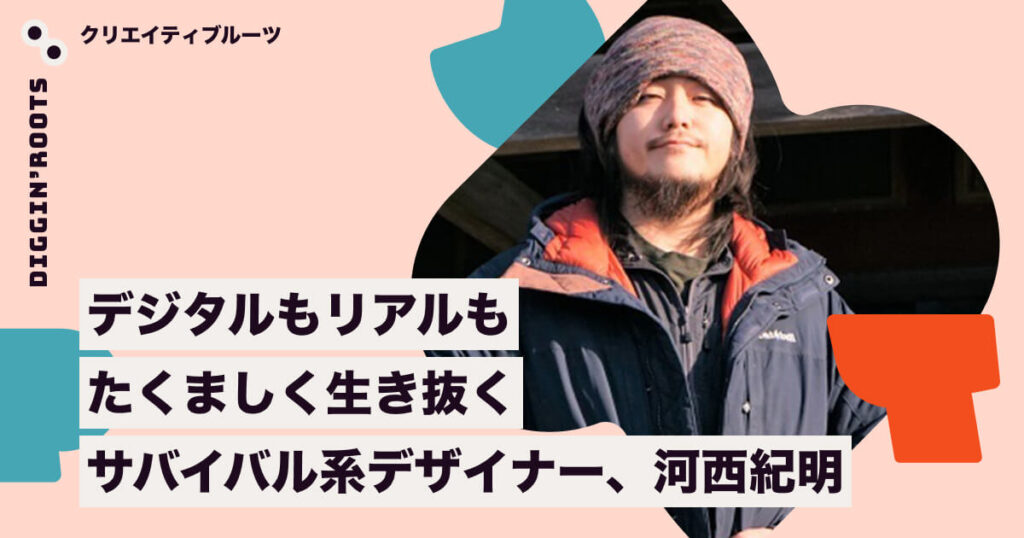
DMMの中の多様な組織を横断しながら、新しい事業の立ち上げや体制づくりをサポート。ビジネスサイドと開発の現場、そしてデザインの3つの職務領域の橋渡しをおこない、サービス設計とチームづくりの両面を成長させる。現在は主にDMMの中ではハイテク寄りの新規事業とデジタル人財の教育事業を中心に担当。「DMM WEBCAMP」といオンラインデジタルスクールのカリキュラムの執筆・監修。
1. 仕事やものづくりへの哲学、こだわりはなんですか?
いつも前提に考えているのは、「デザインに関わる権利は誰にでもある」ということです。
「デザインはデザイナーの仕事」「プログラミングやシステム開発はエンジニアの仕事」と区切って考えてしまうことが多いと思うのですが、それぞれの領域に関わることは本来は誰にでも出来ること。特にデザインは仕事の現場に限らず、何気ない日常のワンシーンなど、どんなところにも存在しているにも関わらず、デザイナーというポジションが暗黙的に専有しているケースが多いです。その結果、「デザイナーが何やってるかわからない」と思われることが長年続いてきてると思うんですね。そこに対して「誰でも関わる権利がある」「みんなでデザインを考えよう」と伝えていきたいです。関わらない理由や障壁をどんどん減らしていく。僕が組織を支援する時も、そういう指針でやっています。僕がいつ抜けても誰でも代わりができる状態にするっていうのが、本来の在るべき姿だと思っています。
これらと同様に「何のためにこの仕事をやってるんだっけ」「このサービスって誰のために作ってるんだっけ」という問いは、デザイナーだけが考えるものではなくて、ビジネスの力も必要だし、エンジニアの開発力もなかったら実現できません。多くの人がデザインという行為に関わることで、その観察やプロセスの実行を通して何かしらの気づきや学びがあり、あわよくば成長に繋がる世界観づくり。そういうのを僕自身が大事にしたいし、周りにも大事にして欲しいなと思っています。

2. あなたが仕事をはかどらせるためにやっていることや、愛用しているものがあれば教えてください。
僕は組織におけるデザイナーの仕事をはかどらせるために、まったく別のベクトルの趣味や仕事をあえて増やしUIデザインやUXデザインの手法や思考プロセスをあてはめて愉しむことがあります。ある種の逃飛行でもありますが組織的な仕事の活動範囲では体験することのない気づきや学習を得る環境や習慣を作るためでもありますね。色々はかどらないことばかりじゃないですか、組織に勤めるって……。
だから、組織や社会的に求められる役割の外で自分でコントロールできるモノ・コトづくりに打ち込む。例えば畑で土を触ったり、見たことのない魚をさばいてみたり、日常でも少しクリエイティブなことに向き合うと充実感が増して、仕事でもストレス耐性が強くなるという感じですかね。
あとは思いもよらないところで仕事がはかどるためのヒントがみつかるのも、仕事以外からが多い気がします。例えば、初めて魚をさばこうと思っても、最初は何から始めていいかわからない。でも繰り返しさばいていくと、徐々にどこに刃を入れたら首を落としやすいか、どうやったらきれいに切りつけることができるか、最終的にどうやって料理したらおいしくなるかを考えられるようになります。
どんどん魚に詳しくなっていくんですよ。そのうちに「この魚は長い歴史を経て特定の環境で生き残るためにこんな骨の形にしたんだ」と。生態や組織、構造への理解や新たな視点の獲得につながっていることに気づきました。
どんな仕事でも目的があり「なぜ」を繰り返していくと、「原理」に行き着くんだなと。サービスの生態、ユーザーの生態も同じように探究心さえあれば理解を深められる。奥の物事を探求する意識が働くというか。そういった日常から気づくことがあるから、忙しくても仕事以外の活動はやめられないですね。普段から農作業や魚の発信をしていると、他の人から「あいつ何やってるんだろう」「農家になったのかな」って思われたりするんですけど……。
河西さんのYoutubeで紹介しているオコゼのさばき方
3. あなたが影響を受けた人は誰ですか?
デザインの原点で言えば、ブルーノ・ムナーリさん。

この方はデザイナーでもあり、絵本作家でもあり、アーティストでもあります。アートやデザインを創造的思考教育という形に発展させたことで有名で、彼の描いた『ABC』『ファンタジア』という絵本が僕のお気に入りです。

自然とデザインの繋がりに関して、この人に影響をすごく受けています。ムナーリさんは自然から親子でデザインを学び、創造的な思考を育んでいけるようなワークショップを提案しています。子供向けのフィールドワークの中にデザイン教育の要素を入れて、「そこに落ちている葉っぱの形が”A”に見えるよね」とか、渦巻いてる花の蔦を見て「これは”8”に見えるよね」とか、自然科学におけるデザインを伝えてくれます。「オウムガイは黄金比率になっている。比率って自然界のものに通じてるところあるよね。そんなところに僕らが人間として美しいと感じるもののロジックがあるんだよ」とか。
僕も元々自然が大好きで、フィールドワークも大好きなんです。そういった繋がりから「この人が伝えていこうとしていることは素敵だ」と思いました。何気なくそこらに落ちているものがアルファベットや記号に見えるなんてことは大人には無いと思うんですよ、意識していないと。でもそこに気づけたら面白いし、「仕事自体は面白くないけど、気付きやひらめきがあれば楽しいのでは?」と思えたら、ちょっと人生幸せになるじゃないですか。そんなことを子供でも大人でもわかるように書いていて、とても影響を受けています。
4. あなたのデザインや考え方のルーツとなったコンテンツはありますか?
「ブッシュクラフト」というアクティビティですね。より自然と一体になれるアウトドアのスタイルです。森などの自然環境の中における「生活の知恵」の総称で、自然の中で生活していく行為そのものや生活に必要な技術を身に着けたりする変え方ですね。
源流は「野営術」のひとつで、ちょっとした備蓄だけで山の中に突っ込んでいって数日過ごすタフなキャンプスタイルみたいな楽しみ方もあります。
不便益という、不便を楽しみ、不便を知って自分達が普段何で満たされてるのかを考えるきっかけになるものの一種です。例えばその山にしか無い素材を使って一日しか使わないようなテントを立てて、何もない状態から火を起こし、ちょっとした備蓄や現地調達でご飯を食べます。
子供のころにボーイスカウトをやっていたので、そのノウハウを実践できています。普段、僕らは気づきませんが現代の世の中のあらゆるものは誰かに便利にデザインされています。もしそれらがなければどうなるでしょうか。その場にある素材や地形など、さまざまな情報をちゃんと自分で理解しないと、その環境で何かを建てて生活したり資源を使って何かを作ることはできないじゃないですか。「石があるだけでこんなに便利なんだ」「ナイフ一本あるだけで人間なんでもできるじゃん」とか、色んなことを知ることによってこんなに可能性が広がるんだと感じます。そういった「知識」と「リソース」をかけ合わせて、ある目的を達成するためのなにかを生み出していくことは、僕の中でデザインそのものだったんですよ。
つまり、紙のデザインだとCMYKやインクの種類、紙の材質とか、配布先の場所にも理解が無いと良いデザインっていうのはできないはずなんですね。それがデジタルになっても同じで、自分の持ってる知識やリソース、そして身につけたスキルは、不確かな環境を生き残る為の術としてでなく、人生をより豊かにする為の「引き出し」になります。
5. 10代の頃に好きだったものやハマっていたことはなんですか?
10代後半に出会って、僕がデジタルのデザインに入るきっかけになったのが『マインクラフト』というビデオゲームです。廃人になるくらいハマりました。

今ではSwitchやアプリでも実装されてるゲームですが、当時はベータ版で別の名前でした。ブロックで色々組み立てていくゲームです。一個一個のブロックに“土ブロック”“木ブロック”などの属性が付いてるんですが、「デジタルの中でもものづくりができるんだ」っていうのに気付いてからはめちゃくちゃハマってりました。仮想空間に自分の街を作ったり、そこに誰かを招待したり。あと、簡単な自動化も出来るので、機械や回路を作ることも可能です。「仮想空間上に何でも作れるんだ」「そこに誰でも入ってこれて、コミュニケーションを取れるんだ」と初めて感じました。
僕、工芸の道を志していたのですが大学生の頃に一度身体を壊したことがありまして。手が震えて、ものが書けなくなって「これ絶対デザイナーで食っていけないだろうな」って思った時に、「デジタルのデザインだったらフィジカルは関係せずに色々と実現できるかも」と思うきっかけになりましたね。10代でゲームを通してデジタルのデザインはちゃんと仕事になると感じられたのはすごく良かったです。
6.最近「いいデザインだな〜」と思ったサービスやWebサイトはなんですか?
僕が最近というか、前からずっと良いなと思っているサービスは「Airbnb(エアビーアンドビー)」ですね。前職を辞めるときにフリーランスになって隠居しようと思ってたんですが、タイミングよくDMM.comに誘われて入社することになったので、そこから金沢と東京の多拠点暮らしになりました。
僕が今住んでいる「黒崎BASE」は、祖父の空き家を改装してゲストハウスをやっています。弟が管理人で、僕がオーナー。ここに拠点を構えながら、コロナ前までは毎週行ったり来たり多拠点生活をしていました。その時にお世話になったのがAirbnb。
色々な地域から人を招いて一緒に田舎体験や観光ができるゲストハウスをやりたかったんですが、当時そんなモデルがなかったんですよ。旅館やペンションは自社の予約ページを作るしかなかったんですけど、Airbnbだったら泊まりたい人たちとすぐに出会える。僕らも石川県で初のゲストハウスとして登録してみたら、本当に1〜2日で海外から10人くらい来るっていう体験をしました。初めて予約を受けてから正味一週間もかからないぐらいでビジネスができちゃったんです。負の遺産と思っていた田舎のおじいちゃんの家がそのままプラスに転じたというか。印象に残る体験をしました。
場所を提供する側と旅の体験を求めてる側とをしっかりと結び付けて、その上で従来の「お客様は神様だ」ではなく、「ホスト側とゲストの相互で一緒に場を作っていこうぜ」っていうAirbnb独自の世界観が確立されている。このあたりは自分がサービスデザインを実践する上でもとても大事にしているところですね。
・・・
関連リンク
DMM.com採用ページ:河西さんが所属するDMM.comでは各種デザイナーを募集しています。Meetyでカジュアルにお話もできます。
DMM WEBCAMP:河西さんがカリキュラムを監修しているオンラインスクールです。
黒崎BASE:河西さんが運営する石川県のゲストハウスです。
D.Tokyo:1on1で河西さんからUXデザインのメンタリングやコーチングを受けられるサービスです。