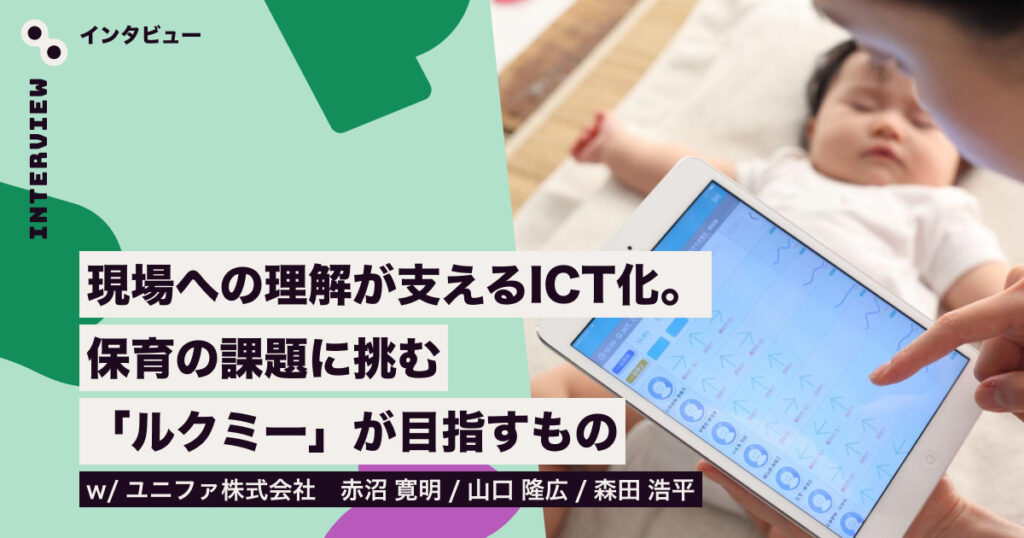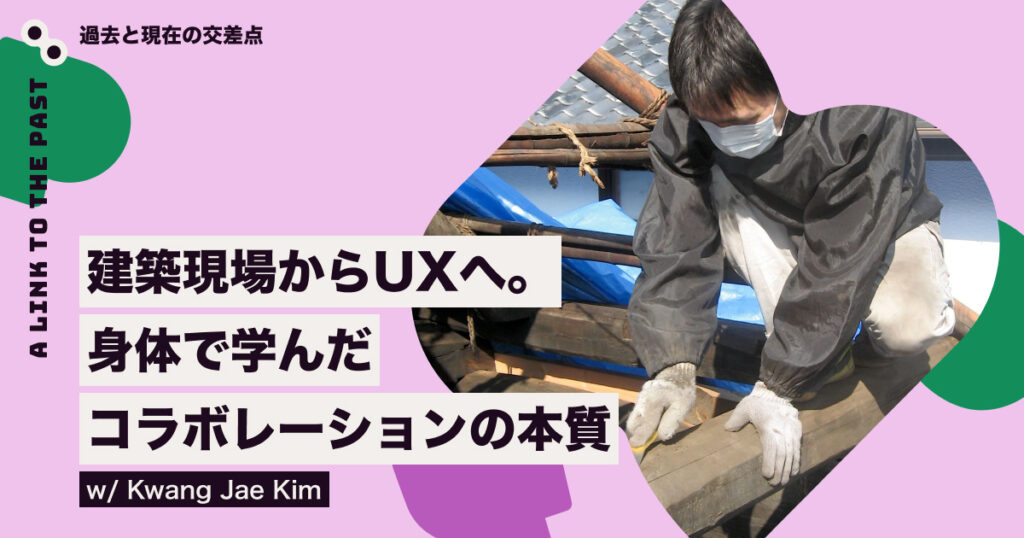スタートアップの“芽”をデザインで支える ベンチャーファンドならではの支援とは

スタートアップに投資する組織、ベンチャーキャピタル(VC)。金銭的な支援に加えて、事業のコンサルティングや現場でのサポートを通じ、情熱を持つベンチャー企業のイノベーションを後押ししています。
ところで皆さん、ベンチャーキャピタルが具体的にどんなことをしているのか、ご存知ですか? 漠然としたイメージだけで理解している人も多いのではないでしょうか。特にスタートアップが身近でない方にとっては、未知の世界かもしれません。
日本には、デザインの思考や技術を軸に、スタートアップへの資金投資や事業支援を行っているベンチャーキャピタルも存在します。今回は、そうしたデザインに特化したベンチャーキャピタル「D4V(Design for Ventures)」でデザインディレクターを務める近藤あすかさんに、具体的な仕事内容や、デザインを通じてスタートアップをどう支援しているのかを伺いました。
近藤 あすか | D4V合同会社 デザイン・ディレクター
McKinseyで新規事業デザインプロジェクトマネージャーとして従事後、D4Vでスタートアップのブランド、プロダクト、組織設計を包括支援。スウェーデンのイノベーションスクール、Hyper Island卒。
デザインで伴走するベンチャーキャピタルの支援スタイルとは
── まず、ベンチャーキャピタルとは何なのでしょうか?
近藤: ベンチャーキャピタル(以下、VC)をシンプルに説明すると「スタートアップ企業に投資をする会社」です。成長段階にあるスタートアップの可能性を信じて、資金という形で支援し、事業の成長に寄り添う存在です。
スタートアップは新しいものを生み出す上で、なにかと資金が必要になります。自己資金だけでは実現が難しいことも多いため、成功に向けて伴走するパートナーとしてVCが機能しています。
起業は何度も経験するものではありません。社会に貢献したいという志があっても、最初はノウハウがなく、戸惑うことも多いでしょう。そんなときに我々を含めたVCが、複数のスタートアップとの協業から得た知見や経験を活かし、壁打ちの相手やアドバイザーとして関わることで、起業家がやりたいことの実現をサポートすることがあります。
── なるほど、金銭面だけの支援ではないのですね。ここでいう「スタートアップ企業」とは、なにか定義があるのでしょうか?
近藤:我々の場合、短期間で急成長して企業価値を高め、最終的に買収や株式公開(IPO)等のエグジットで大きな利益を生む可能性がある企業と定義しております。
世の中に顕在化していないニーズを取る、あるいは形作るところから事業を作っていくため、黒字化に至るまでにはある程度の初期投資が必要です。だからこそスピード感が重要で、そのために資金調達が不可欠なのです。そういった企業を支援しているVCが多いのも、この理由からです。
社会的に必要とされるサービスやプロダクトは、できるだけ早く実装されることが望まれます。その点が、一般的な中小企業とスタートアップとの大きな違いかもしれません。
── VCの中でも、D4Vにはどんな特徴があるのでしょうか?
近藤: D4Vは「Design for Ventures」という名前のとおり、デザインが事業成長のレバーになると信じており、デザインを軸とした支援に注力しています。これが、他のVCとの大きな違いだと考えています。
我々はデザインコンサルティングファームであるIDEOとパートナーシップを結んでいます。IDEOは、デザイン思考を世の中に広めた会社で、デザインが事業にどのように貢献できるかを豊富に経験してきました。デザイン思考は大企業に限らず、スタートアップにおいても有効です。
D4Vでは、デザインを戦略に取り込んだ支援を行い、事業と共に成長していく取り組みを行っています。一般的なVCが重視するのは財務や市場といった数値的な視点かもしれませんが、我々はそれに加えて、体験やチーム、ストーリーといった数値化しにくい価値にも目を向けています。
具体的には、サービスやプロダクトの在り方、従業員の体験、パートナーやステークホルダーとのコミュニケーションまで含めて、事業が実際に成長するための支援を行っています。

デザインコンサルティングとの違いは「スピード感」
── D4Vの中でも近藤さんはデザインディレクターとしてご活躍ですが、具体的にはどのような役割なのでしょうか?
近藤: いろいろと携わっていますが、大きく分けると「出資前に行うこと」と「出資後に行うこと」の2つに分類できると思います。
まず、出資前にはデューデリジェンス(Due Diligence)を行います。簡単に言えば、投資の判断をする前に、その会社の状態を徹底的に調べるプロセスです。ビジネスモデルの妥当性、チームの状況、財務や法的観点、市場の将来性などを総合的に検証し、投資すべきかを判断します。
その中でもD4Vでは、デザインデューデリジェンスという独自の視点で評価を行っています。ユーザーや社会に対してどんな価値を提供したいと考えているのか、そのビジョンや、それに基づくプロダクト・サービスの構想を理解した上で、「それが実際に実現可能なのか?」というデザイン観点からの見極めを行います。また、デザインによる事業インパクトへの共感や、顧客への価値提供ができそうかといったチームのデザインへの興味関心の有無も確認します。
そして出資後には、デザインの視点からの支援に入ります。たとえば、ユーザーにどのような体験を提供するか、接点となるコミュニケーション設計の支援、それらを自走、継続可能な組織として設計することまで支援範囲に含まれます。私はそういった現場に、PMのような立場で関わることが多く、D4Vのネットワークから適切なデザイナーを見つけ、チーム編成をサポートすることもあります。
── 近藤さんがVCでデザインディレクターとして働こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
近藤: スタートアップで事業を立ち上げる経営者の方々は、本気で世の中を変えたい、なにかを創りたいと考えてチャレンジされています。そういった方々ともっと近い距離で仕事がしたいと感じて、VCであるD4Vに入社しました。
前職でも新規事業開発のコンサルティングなどに関わっていましたが、より密接な関係で関わりたい気持ちが強くなっていました。
もうひとつの理由は、私自身がいつかは自分で事業を立ち上げてみたいと考えていることです。さまざまなスタートアップの方々とご一緒させていただく中で、多くの学びを得たいと思っています。
実際に一緒に仕事をしてみて、日々多くの学びがあります。表面的に見える課題と、組織内部で直面している本質的な課題には違いがありますし、事業の種類や業界、組織の在り方によっても状況は大きく変わります。
弊社は70社以上の会社に投資していますが、課題は本当に多種多様です。すべてのミーティング、すべてのコミュニケーションから新しい気づきを得ています。
── デザインコンサルも、デザインを通じて事業をサポートする点では共通しているように感じますが、どんな違いがあるのでしょうか?
近藤: IDEOのようなデザインコンサルティング会社とD4Vは、どちらも「社会になにかしらの価値を生み出すために伴走する」という点では共通しています。ただ、最も大きな違いはスピード感かもしれません。
IDEOでは大企業を対象とするケースが多く、中長期的な視点や未来を見据えたデザインを考える機会が中心です。一方、D4Vではスタートアップという小規模組織への支援となるため、未来を見据えつつも、限られた資金やリソースの中で短期的な成長を見せる必要があります。
「今、なにをすべきか」「将来に向けて、なにを準備しておくべきか」、 そのバランスを見極めながら支援するのがVCならではの役割だと感じています。
どちらも最終的には「社会にとって良いものを生み出す」「人々の暮らしを豊かにする」といった目標を掲げていますが、その到達までのプロセスや向き合い方には違いがあります。

スタートアップにデザイン支援が必要な理由とは
── 支援先となる会社は、どのように決めているのでしょうか?
近藤: まず軸になるのは、その事業が今の国や社会に必要とされているかどうかです。そしてもうひとつ、我々の場合は「デザインの力によって事業の成長が加速する可能性があるか」も大事な判断材料としています。投資によって価値を提供できる、そしてその企業を成長させることができればいいなと考えています。
特定の業界に限定しているわけではなく、ヘルスケアやエンタメ、BtoBのSaaSなど幅広い領域を支援しています。主に「アーリー」と呼ばれる創業間もない企業が中心です。
── そうした企業の方が、デザインの力がまだ足りていないと感じることが多いのでしょうか?
近藤: そうですね、そのようなケースが多いです。
多くの企業が「人のためになにかしたい」という想いからスタートしていて、顧客を中心に考えて事業を進めています。ただ、ユーザーに届けたい価値をどのように体験として設計するか、具体的にどんな手段があるのかまでは見えていないことがほとんどです。
私たちは、アジャイルなデザインアプローチを用い、顧客の声を素早くサービス体験へと翻訳し、プロトタイプとして形にしながら実際にテストを重ね、より良い解決策へと磨き上げていきます。こうした支援へのニーズが高いため、アーリーステージのスタートアップにできるだけ早く関わるようにしています
── デザインに馴染みがある人にとってはユーザー中心設計は当然でも、実践している企業はまだ少ないんですね。支援があるのはとても心強いと感じました。
近藤: デザイナーが在籍している会社はまだまだ少ないですね。これまで多くのスタートアップを見てきましたが、比率で言うとデザイナー1人に対してエンジニアが5人くらいのイメージです。デザインの力を必要としている企業が多いからこそ、我々の支援に価値を感じてもらえたら嬉しいです。
── スタートアップに共通する課題はありますか?
近藤: いくつかあります。
ひとつは先ほども触れたように、顧客ニーズは把握していても、それをサービス体験やプロダクトに落とし込めないこと。そして、開発にあてる人的、金銭的なリソースが不足しているという声もよく聞きます。
さらに、特に経営者の方が考え抜いて考えた仮説となると市場の変化に応じてピボット(方向転換)をすることが難しいという課題も感じます。
ピボットの難しさについては、とても共感しています。経営者の皆さんはとても優秀で、本来はピボットする力もあるはずです。ただ、人からそれを指摘されると、腑に落ちないと感じてしまうこともあるようです。いろいろな相手に価値を届けたいと考えている中で、それがしっくり来なければ、私たちは「顧客の声」として丁寧に伝えるように意識しています。
また、経営者の方々からよく聞くのは、「経営はチームで進めるものだけれど、実際は孤独だ」という言葉です。その孤独に寄り添うのもVCの役割だと思っています。温かい言葉や励まし、インスピレーションになる話を届けることもあれば、必要に応じて耳が痛い指摘をすることもあります。少し“お母さん”的な存在なのかもしれません。
── 支援する相手は、若い方が多いのでしょうか?
近藤: 実はそうでもありません。大学を中退して事業を始めた20代前半の方もいれば、豊富な経験を積んだうえで起業される50代の方もいらっしゃいます。
「経営者」とひとくくりにしても、パーソナリティも違えば、組織の運営方法もさまざまです。どれが良い、悪いということではなく、その人らしさが会社らしさにつながっているのだと思います。

新たな価値の芽吹きに伴走する喜びと難しさ
── 支援先の企業とうまくいかないこともありますか?
近藤: 「合わない」と感じることは、ほとんどありません。スタートアップで働く方は、対話を通じて考えを変えていく柔軟性を持っていることが多く、衝突するようなことはあまり起きませんね。仮に意見の違いがあっても、最終的な決定権は企業側にあると考えています。
私たちが投資を決める際に大事にしているのは、「そのチームを本当に信頼できるかどうか」です。「このチームならきっとやり遂げられる」と信じたうえで投資しています。そのため、私たちの視点や考えは共有しつつも、最終判断はあくまで会社に委ねています。
── VCで働く面白さと難しさには、どんなものがありますか?
近藤: 幅広い業界に携われること、そしてまだ世の中にない価値を生み出していく過程に関われることが、この仕事の魅力です。スタートアップという“種”が少しずつ芽を出し、育っていく様子をすぐそばで見られるのは、なによりの楽しさですね。
また、会社ごとにまったく違う問いの立て方や文化のつくり方、組織の課題に触れられるのも面白さのひとつです。
一方で難しいのは、「どこまで踏み込むべきか」というバランス感覚です。外部の立場だからこそ見える観点を持ちつつも、創業者や経営者の想いを汲み取り、適切な距離感で成長を後押しする必要があります。
VCとして、事業のために必要な変革を推進する責任を負いながらも、相手の信念と衝突しないように着地させる。その「ちょうどよさ」を探るのは、簡単ではありません。
デザインと経営を結ぶために、誰よりもユーザーの代弁者であれ
── デザインを社内に浸透させることに苦労しているインハウスデザイナーは多いですが、多くの組織を見てきた近藤さんから見て、経営者やチームメンバーにデザインを理解してもらうためのコツはありますか?
近藤: 自社の経営課題に、デザイン思考を応用してみることは非常におすすめです。デザイン思考やデザイナー的な視点とは、ユーザーがなにを求めているのか、どんなインサイトを持っているのかを起点に、体験やプロダクトへ落とし込むものです。これを応用して、経営者をユーザーと見立ててみるとよいと思います。
経営者がいま抱えている悩みや課題をヒアリングして、デザイナーとしてどう動けば喜ばれるのかを考える。それを起点にコミュニケーションを取ることで、うまく関係性が築けるケースが多いと感じます。
また、自分の意見を「ひとりのデザイナーの主張」としてではなく、「顧客の声に基づく仮説」として伝えることも大切です。実際に顧客からヒアリングした情報をもとに検証を行い、「この施策にはこういった効果が見込めそうです」と説明できると、説得力が高まります。
たとえば、「インターフェースのここを改善したらこうなりました」という事後報告ではなく、「チャーンレートを10%下げるためにこの施策を検討しています。その仮説を検証するためにABテストを実施したいです」といった提案型のコミュニケーションを心がける。経営者から見て、なぜそのデザインが必要なのかが理解できると、支援や共感を得やすくなります。こうしたわかりやすい伝え方が、デザインの重要性を認識してもらうきっかけになると思います。
── 課題や問いから逆算して提案するスタイルですね。
近藤: そうですね。そして、経営者と同じ言語で話すこともとても重要な要素だと思います。経営者はみなさん数字に向き合っている立場なので、株主や社外に向けて提示すべき数値の観点から、自分のデザイン業務がどう貢献しているのかを説明できると、理解が深まります。
── スタートアップに関わるデザイナーに求められるスキルやマインドセットには、どんなものがありますか?
近藤: 単に言われたものを作るのではなく、経営課題を理解しながら、事業を一緒につくっていこうとする姿勢がとても大切です。スタートアップの現場では、メンバーが忙しく、経営者も細かい指示を出す余裕がないことが多いです。
そんな中でも、「このデザイナーに任せれば大丈夫」と思ってもらえるような存在になれること。今の会社フェーズやチームの状況を踏まえ、「いまなにが必要なのか?」を自ら発見し、自律的に動いていける方が向いていると思います。
もうひとつは、ユーザーの代弁者であること。経営者が数字に追われがちな場面でも、常に顧客の視点をアップデートし、それを事業の方向性に反映させていく。その橋渡しの役割は非常に重要です。
ユーザーの声をしっかり受け取り、それをサービスや機能へと変換していく。実行フェーズの中心に立って進めることができるのは、大きな価値になると思います。
── 近藤さん、たくさんのお話をありがとうございました!
取材協力
D4V合同会社 https://d4v.com/jp