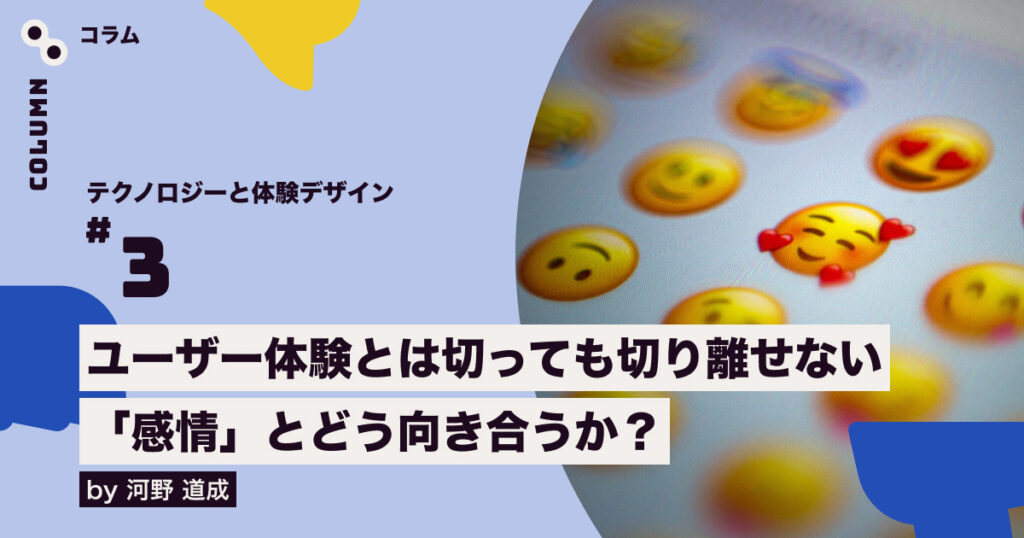経営者は本当に孤独なのか? 経営会議をオープンにしてみた話
Designing Well / ウェルビーイングをデザインする #1
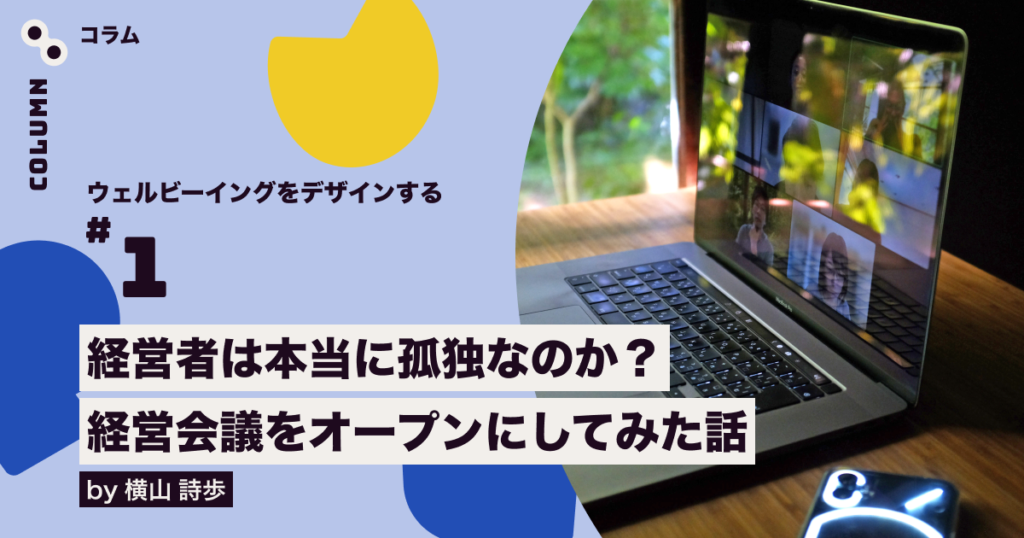
経営とは意思決定の連続です。
筆者はCXO(Chief Experience Officer)の立場からスタートアップの経営に参画し、1年半が経ちます。Nestoというサービスを立ち上げから奔走し、アーリー期と言われる事業を成立させるため悪戦苦闘しているフェーズです。
焦りは常にあります。減っていくキャッシュ。目標通りにならない数字。限られた時間の中で、なるべく多くのことにトライしたい思い。迅速な会社運営へのプレッシャー。敏速さや量が求められることは事実です。しかし、行き急ぐことが最良の意思決定につながるのか、最近私は疑問を持つようになりました。
「早く行きたければ、ひとりで進め。 遠くまで行きたければ、みんなで進め」という言葉があるそうです(アフリカのことわざと言われていますが出典は不明です)。この「みんなで進む」というところが難しいのです。より多くの人間を巻き込み、知見を活かすことでよりよい意思決定ができる反面、スピードが損なわれます。
「ひとり」のスピード感と「みんな」の賢さ、これらの両立ができる仕組みを目指すためにはどうすればいいのか。私たちのNestoではよりよい意思決定のための広い視野を持ちつつ、なおかつ適切な速さをキープする仕組みについて試行錯誤をしています。
まだまだ道半ばではありますが、ひとつの実践例として私たちが取り組んでいる「オープン経営会議」について共有します。
経営会議をオープンに

Nestoでも色々と試行錯誤してきました。「社長の独裁時代」や「全員で意思決定をしてスピードが遅い時代」など、紆余曲折を経て現在のNestoでは「広い視野で検討をしつつ、個人が意思決定をする」スタイルの組織運営となっています。つまりフルコミットで担当領域を持っているメンバーは、基本的にはなんの相談もなしに意思決定ができるということです。随時報告をしているとはいえ、これはお互いを信頼しているからこそできることです。Nestoではこの信頼関係の構築に1年以上かかりました。
私たちはひとりひとりがより質の高い意思決定をすることと、ステークホルダーとの信頼関係を築くことがより良い経営につながると思っています。それを実現させる仕組みのひとつとして「オープン経営会議」を実施しています。
オープン経営会議の特徴は、従業員や株主のみならず、ユーザーも参加できること。これがこの会議を「オープン経営会議」と呼んでいる理由のひとつです。コンプライアンスの観点などから一部情報は別扱いとしているものの、出席したユーザーは週次のNestoの動きをほぼすべて知ることができます。
オープン経営会議では、主に経営メンバーがその週に自分が取り組んだことや次週の動きについて話します。参加者は自由にコメントができます。「私だったらこうすると思う」「こういう観点は考えた?」「これすごくいいね」「こっちの方が筋がいいと思うな」「ここは一緒にやれるといいかも」といった類のものです。コメントを受けた本人はそのコメントを活かしてもいいですし、無視しても、掘り下げても、協力を仰いでもいい。
Zoomのチャットに自由に書き込んだり、最後に参加者からのコメントの時間をとっています。後日メッセージをもらったこともあります。しかし、前述のように必ずしもそういったコメントを反映させるわけではありません。それはユーザーであれ、他の経営メンバーであれ同じです。一番コンテキストを理解している本人が、本人の責任範囲で意思決定を行います。

オープン経営会議のメリット
1. 視点が増える
参加者のコメントを聞くと、単純に「なるほど」と思ったり「こっちの方が筋がいいかな」など参考になることが多いです。ユーザーの肯定によって勇気がもらえることも多いです。
ひとりでの観点の検討には限界があります。単純にさまざまな立場の視点があればあるほど、より良い意思決定につながります。
ヨハンノルベリ氏の『OPEN』のなかでこのような一節がありました。
集団は多様性があるほうが問題解決がうまくなる。そうした集団では摩擦も大きい。だれかが前提を疑問視したり、手早い解決策に反対したりするし、おかげでプロセス全体がギクシャクして、不快になる。だがそれだからこそ、まさにそれが必要なのだ。あまりに同質な集団は、集団思考にすぐに陥ってしまう――反対の声は上がらず、別の道筋は検討されず、集団はおもに既知の思いこみに沿った情報ばかり探すようになる。みんな自己検閲して、トラブルメーカーと思われたり、なにか不測の事態でスケープゴートにされたりしないようにすることも多い。
ヨハンノルベリ著『OPEN(オープン):「開く」ことができる人・組織・国家だけが生き残る』より
悶々と同じメンバーで考え続けていると、想定が同質化されていきます。少しでも外の立場からの意見があることで考えは深まり、別のやり方に気づくことができると感じています。
自分とは異なる意見を受け胸に刺さることもありますが、多角的な検討こそが質の高い意思決定につながると感じています。
2. 意思決定スピードを保てる
「オープン経営会議」を始める前からNestoでは、経営会議とは別に3ヶ月に1回「Nesto総会」をやっています。こちらは経営メンバーと株主をメインとしながら、働いているメンバーやユーザーが参加することができます。そこでは数字進捗や施策の振り返り、目標などについてお話ししています。わかりやすいコミュニケーションになるよう、資料をまとめるなどある程度の事前準備やすり合わせも行っています。
対して、オープン経営会議の場合は、そのようなおもてなしはありません。経営メンバー向けにやっている経営会議で、参加者はほとんどの時間ただ聞いてるだけです。参加者がいてもいなくても、どちらにせよやっていることなので準備は必要ありません。ステークホルダーに向けた特別なコミュニケーションの場を開いているのではなく、普段経営メンバーがやっていることをそのまま開いているだけなので、時間がなくてもできる施策と言えます。
それまでは、コンテキストの理解が不十分な人を経営プロセスに巻き込むと意思決定に時間がかかる、と後ろ向きな思いがありました。しかし、プロセスをオープンにするからといって、全員の意見を反映させなければと躍起になる必要はないと実感し、現在は担当者が責任と裁量を持って行えば意思決定のスピードは保てていると感じます。
3. 信頼関係が築ける
すべてのステークホルダーが積極的に経営を知りたい、関わりたいと思っているわけではありません。Nestoでもオープン経営会議にまでくる方はほんの一部です。
しかしやってみて気づかされたのは、ユーザーであっても働いてるメンバーであっても熱量が高い人はいるということです。いまではそういった方々に参加の機会を与えないのは機会損失だと思うようになりました。
オープン経営会議に来ていただくと、参加者も経営のコンテキストをある程度理解できるようになると実感しています。全体像やコンテキストを理解して、その上で考えてくれる仲間が増えます。これは双方にとって大きなメリットです。
「悪い知らせは早く言え」とビジネスではよく言われます。早い方がアドバイスや介入がしやすいからです。まったくもってその通りだと思いながら、当事者としては「いまやってるこれがもしかしたらうまくいくかもしれないから、この結果が見えてから言おう……」といった思考にどうしてもなりがちです。オープン経営会議をやるようになって、悪いニュースも早めに周りに共有するクセの練習になり、自分自身のメンタルが鍛えられているような気もします。
自分が信頼したいと思える会社なのか。企業の姿勢がますます問われる時代になってきているように感じます。私の好きな会社は同じくオープンな取り組みをしています。たとえば、デジタルプロダクトメーカーである「Nothing」は「コミュニティーボードメンバー」というユーザー代表として経営会議に出席する制度を設けていたり、デジタルコンテンツ売買のプラットフォーム「Gumroad」ではボードミーティングをYouTubeにアップロードし誰でも見られるようになっています。そういったオープンな姿勢への共感が、私自身がそのブランドやサービスを選ぶ理由につながっています。安心感や信頼感が持てるスタンスは常に問われています。

孤独な経営者に対する救い
オープン経営会議はより良い経営を目指すための手段のひとつにすぎません。
オープン経営会議で巻き込むことができるのは主に熱量が高い一部の人であり、かつ経営目線からすると比較的受動的な施策です。熱量が高い人や声を上げてくれる人だけを見ることで、多角的な視点から遠ざかってしまっては逆効果です。Nestoにおいても現在ヒアリングの仕組み化など、能動的な施策との掛け合わせで設計をしています。
ただ、受動的だからこそ「経営の一部をオープンにする」のは取り入れやすいのではないでしょうか。やる前は「うちの社員やユーザーはきっと経営なんて興味がないと思う」と思うかもしれません。Nestoでも当初は本当にオープン経営会議に人が参加するとは思っていませんでした。
「経営者は孤独だ」とよく言われています。
スタートアップ経営のむずかしさは日々感じています。志を持ってスタートしたものの、数字の成果に現れてないときなど、信じてくれている人たちに申し訳ない、不甲斐ない気持ちを持つ場面も多いです。その上で、一緒に未来を考えてくれる仲間がいる感覚があります。オープンな態度にしていくことで、仲間が増え、頑張る理由が増えている。孤独ではないと思える。実際のところ、オープンな経営にすることで一番救われているのは私たち経営者なのかも知れないと思っています。
すべてを最初からオープンにする必要もありませんし、オープンにすることだけが手段ではありません。どうやったらより多角的な意見をもとに意思決定ができるか。熱量が高い方を仲間に巻き込めるのか。これを読むみなさんの工夫もぜひ教えてください。