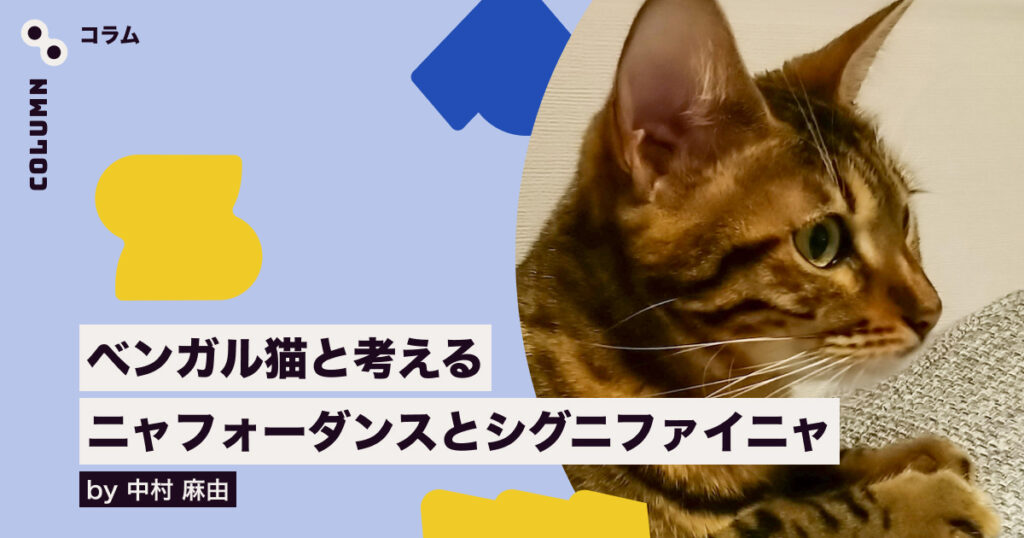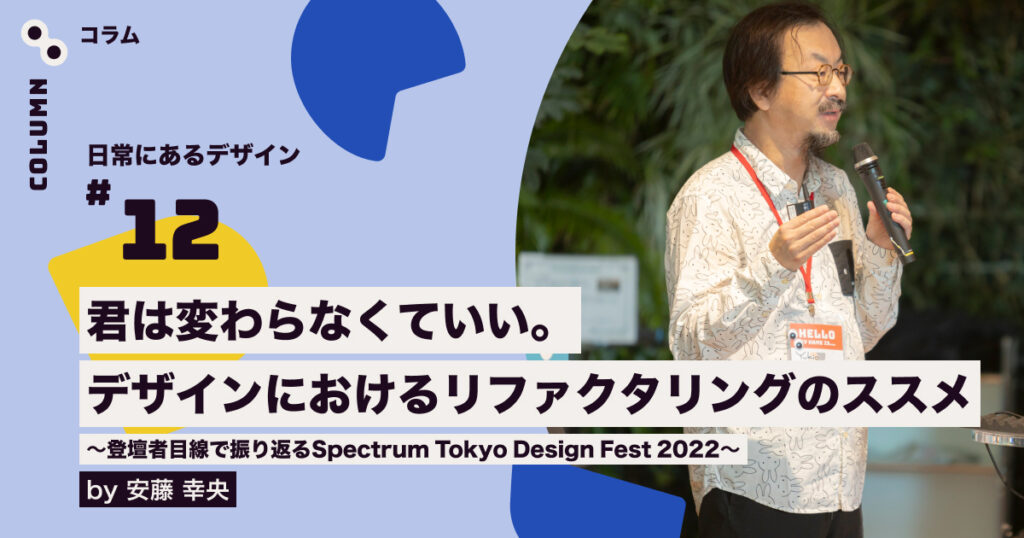待つことのデザイン

瞬間が変える時間の体験
世の中は「待ち時間」にあふれています。スマホアプリが起動するまでの数百ミリ秒、Webサイトが読み込まれる間の数秒、見たい動画を見る前のスキップ不可の30秒の広告、エレベータのボタンを押してから待っている数十秒、カップラーメンにお湯を入れてできるまでの3分間、昼休みに行ったランチのレストランで注文してから食べ物が出てくるまでの十数分、約束の時間を過ぎてもなかなか来ない待ち合わせの相手……。なにかを待っている間、私たちの時間感覚は物理的な時間とは異なる速度で進みます。
特に現代の人々にとって「待つ」という感覚はかつてないほど短縮されています。スマートフォンの普及と共に、情報や刺激を即座に得ることに慣れてしまい、わずか数秒の待ち時間でさえイライラを覚えるようになりました。京都駅前の歩行者用信号の待ち時間は1分ですが、東京駅前の歩行者用信号は20秒です。信号が変わるのを待つ数十秒間ですら、多くの人々はスマートフォンを取り出し、「暇な時間」を埋めようとします。幼児に至っては、観たい動画の本編が始まるまでのほんの数秒のローディング時間に「まだ? まだ? 」と催促することも珍しくありません。
「待つ」という忍耐力が社会全体で低下しつつある昨今、デジタルプロダクトの体験における待ち時間のデザインはかつてないほど重要になっています。ほんの一瞬にどういう意味を持たせるか、時間の断片の組み合わせがユーザー体験全体を大きく変える力を秘めているのです。
知覚時間と実時間のギャップ
人間の脳は物理的な時間をそのまま認識しているわけではありません。同じ5分間でも、退屈な会議中の5分と好きなドラマを見ている5分では、まったく異なる長さに感じられます。最近人気のアニメ作品を何度も繰り返し観ている友人は、ストーリー展開が素晴らしすぎて1話25分の視聴は体感5分の感覚だと言っています。
相対性理論で知られるアインシュタインはこの現象を見事に表現しました。「魅力的な人と一緒に過ごす1時間は1分のように感じるが、熱いストーブの上に1分座れば1時間のように感じる。それが相対性だ」と。この「心理的時間」と「物理的時間」の違いはデジタルプロダクトでの体験をデザインする上で重要な要素のひとつです。体験において「待たせない」のが一番ですが、待たせざるを得ない場合は「待つこと」をデザインするのです。
ディズニーランドでは、アトラクションの待ち時間さえも魔法の一部。「キューライン」と呼ばれる待機列には、物語の世界観を感じさせる装飾や音楽が施され、長蛇の列に並びながらもアトラクションのプロローグを体験でき、物語への期待が膨らみます。このキューラインは常時計測されており、最適化の工夫がなされているそうです。
こういった「待つ」時間の感覚は主に2つの要因に影響されます。ひとつは「処理する情報の量」であり、もうひとつは「注意の分散度」です。新しい情報が多い場合や集中しているときには時間が短く感じられ、退屈であったり不安なときには時間が長く感じられるのです。
この知見をデジタルデザインに応用すると、待ち時間をポジティブな体験に変える鍵が見えてきます。たとえばよく見るダウンロードやファイルコピーなどの待ち時間に現れるプログレスバーは単なる進捗表示だけではありません。ユーザーの時間認識に寄り添う待ち時間の提示ともいえるでしょう。特に工夫されたプログレスバーでは、初めは速く、後半でゆっくりになる非線形に進むよう細かな調整がされており、一定速度のものよりも時間を「短く」感じられることがわかっています。これは、脳が時間の経過を予測し、その予測との差分を考えながら脳の中で時間感覚を得るためです。
マイクロモーメントという考え方
こういったデジタル体験における短い時間の制御は「マイクロモーメント」という概念でまとめられています。マイクロモーメントは2013年頃からUXデザインの世界で注目されるようになりました。マイクロモーメントは、ユーザーの操作に対する繊細な反応や、
システム状態の変化を視覚的に表現する小さな瞬間のことを指します。スマートフォンのボタンをタップした際の微妙な凹み感、メニューが開く際のなめらかな展開アニメーション、フォーム入力時にすぐに内容をチェックして入力間違いを知らせるといった動作。これらはすべて意図的にデザインされたマイクロモーメントです。
ディズニーアニメーションの原則は、デジタルインターフェースのマイクロモーメントにも応用されています。たとえば「予備動作(Anticipation)」の原則は、登場キャラクターが主要なアクションの前に反対方向への小さな動きを入れることで、ユーザーの注意を引き動きを予測させる効果を高めます。こういったアニメーション制作のノウハウは現代のマイクロモーメント設計にも脈々と受け継がれています。
マイクロモーメントは単なる視覚的装飾ではなく、情報を伝え、ユーザーの注意を導き、感情に訴えかけ、ブランドの個性を表現するなど重要な役割を果たします。そしてなにより、待ち時間をいかに短く感じるか、直接影響を与えるのです。
待ち時間を変える魔法の400ミリ秒
人間の認知の仕組みにおいて、およそ400ミリ秒(0.4秒)という時間には特別な意味があります。(※1982年にIBMの研究者Walter J. DohertyとAhrvind J. Thadaniが提唱したDoherty Thresholdに基づく)これは私たちが「即時」と認識できる最長の時間です。現実には、この閾値が実は固定的ではなく、利用者の置かれている状況、年齢、使用しているデジタルデバイスの種類によって200〜600ミリ秒の範囲で変動することが示されています。特にスマートフォンやタブレット端末などモバイル環境では、この閾値が平均で15%短くなる傾向があるといいます。
この知見は非常に重要です。たとえばモバイルアプリのデザインでは、デスクトップ版よりも素早く反応する必要があります。また、ユーザーが急いでいる状況(例:朝の通勤時間)と余裕のある状況(例:リラックスした夜)では、同じスピードのアニメーションでも異なる印象を与える可能性があるのです。
マイクロモーメントの実践的テクニック
では具体的にマイクロモーメントを操る達人になるにはどうしたら良いのでしょう? 以下にいくつかのテクニックを紹介します。
イージング関数の工夫
アニメーションの心地よさは「加速・減速」の設計で決まります。特に「ease-out」は、自然さと反応の速さを両立でき、直感的な操作感を演出します。
多感覚フィードバックの活用
視覚、聴覚、触覚を組み合わせることで、操作の確実性と満足感を高められますApple Payの決済や、X(旧Twitter)のハートのアニメーションと振動の連動はその好例です。
段階的な情報開示(プログレッシブ・ディスクロージャー)
読み込み中のレイアウトを骨組みだけ表示するSkeletonスクリーンのように、処理中でも何かが進んでいる印象を与えると、ユーザーの不安や苛立ちを和らげます。
能動的な待機時間の設計
待ち時間も体験に変える。Instagramで写真アップロード中の別操作の許容や、処理中に遊べるミニゲームなど、「待つだけ」を避ける工夫が有効です。
状態変化の予告演出
ボタンの色の変化 → 処理実行といった段階演出は、システムの反応を視覚的に伝え、安心感を与えます。
一方、マイクロモーメントの過剰使用は注意疲労を引き起こします。すべての操作に派手なアニメーションを付ければ、最初は印象的でも次第にユーザーはそれらを無視するようになり、重要な通知も見逃す危険性が高まります。効果的なマイクロモーメントのデザインは、インターフェース全体を「注意を集めるための要素」として捉え、各要素の重要度に応じた動きをデザインする必要があります。日常的な操作には控えめな動きを、重要な出来事には印象的な動きを割り当てるといった具合です。
日常のマイクロモーメント
技術の進化とともに、マイクロモーメントの可能性も広がりつつあります。AIによる予測型インターフェースでは、ユーザーの次の行動を予測し、適切なタイミングで必要な情報を先読みすることで、待ち時間自体を最小化する試みが進んでいます。
優れたマイクロモーメントは、その存在自体が意識されないことが多いものです。ユーザーは「このアプリは使いやすい」「このサイトは心地よい」と感じるだけで、その背後にあるマイクロモーメントの存在に気づかないこともあります。
これはある意味で、マイクロモーメントデザインの成功といえるでしょう。あまりに目立てば邪魔になり、存在しなければぎこちなく感じる。その繊細なバランスこそが、マイクロモーメントデザインの絶妙な良さなのです。
日常の体験で、ふと「これは、なぜ心地よいのだろう」と考えてみてください。そこには、おそらく緻密に設計されたマイクロモーメントの魔法が働いているはずです。時間という最も貴重な資源をめぐる体験をデザインすることで、何気ない「待ち時間」さえも味方につけるのです。
・・・
「A Design in the Life / 日常にあるデザイン」では、生活の中のデザインと、デジタル空間のデザインとの両方の切り口で、デザイン体験の解像度を上げる視点を提供していきます。
なにか取り上げて欲しいテーマやご希望などがございましたら、ぜひ編集部までお知らせください。