「良い問い」からはじまる5つの対話。「Yoitoi Summit 2025」セッションレポート
2025年7月19日にGMO Yours・フクラスで開催された「Yoitoi Summit 2025」。「良い問い」と「酔い問い」が入り混じる場を通じてデザインの可能性の探求をめざした本イベントでは、7つの問いを軸にトークセッションが繰り広げられました。本記事では、日本語で展開された5つのセッションの様子を、登壇者の印象的な一言にもフォーカスしながらお届けします。

なぜチームの意思決定はこんなにも難しいのか?
【登壇者】
・デザイナー 長谷川恭久さん
・Newbee株式会社 プロダクトマネージャー 蜂須賀大貴さん
Yoitoi Summit最初のセッションは「なぜチームの意思決定はこんなにも難しいのか?」。その幕開けを飾ったのは、長谷川さんの痛烈な一言でした。
デザインの世界でもよくあるじゃないですか、小奇麗な概念図。ああいうのって、本当にろくでもないなと思っていまして。(長谷川)

美しいバランスからなる意思決定は机上の空論であることが多く、実践の世界はどこまでも泥臭いもの。またそういった理想像や概念には、欧米流の強い意思決定者の存在を前提としたものが多いため、「日本の現場にフィットしにくいのでは?」と投げかけます。本当の意味での「意思決定の責任者」はいるのか? 長谷川さんは、「日本の組織には、意思決定者をあやふやにしがちな傾向がある」と指摘します。
蜂須賀さんは、こんな視点も重ねました。
そもそもチームで意思決定したいのかというと、そんなことないと思うんです。誰よりも市場とユーザーを捉えていて、強いリーダーシップを発揮する人がいれば、それで良いんじゃないかって。(蜂須賀)

不必要な配慮、情報の不透明さ、責任の所在の曖昧さ――そういった日本の組織の意思決定を必要以上に複雑にしている要因が、ふたりの議論を通じて浮かび上がってきました。
ではこの先、意思決定のあり方はどのように変化していくのでしょうか?不確実性が高く、先が不透明な時代における、意思決定者の存在価値に思いを巡らせます。最後にふたりから飛び出したのは、覚悟やエゴといった言葉でした。
結局何もわからないんだから、「俺はこれをやる」と覚悟を持って言えばいい。「いい奴」であれば任せてもらえるでしょう。エゴを持ち、覚悟を持って意思決定する人がいれば、物事は前に進むんです。(蜂須賀)
みんなの声を受け入れたデザインをしていくだけでは、プロダクトデザイナーには未来がないような気がします。「敢えて声に反して、我々らしいデザインをしてみよう」と問いかけのできるマインドセットが必要です。(長谷川)
これからの時代、「強い意思を持って選び取る力」こそが人間の仕事になっていくのでしょうか? 非合理であっても、情熱的な意思決定こそが人を惹きつけるのかもしれません。そんな、人間らしい意思決定の価値をあらためて考えたくなるセッションでした。
デザインの民主化は組織に何をもたらすのか?
【登壇者】
・GMOペパボ株式会社 マネージャー/シニアデザインリード 山林茜さん
・BASEYARZ Group代表・ソーシャルクリエーター 河西紀明さん
誰もがデザインに関わる時代、デザインの仕事はどう変わっていくのでしょうか? 議論のなかで浮かび上がったのは、民主化によって生じた「無関心・無関与」の危険性です。
あるべきデザインを考え、合議するプロセスに参加しない・できないデザイナーが増えるほど、無関心・無関与として問題視されていくと思うんです。言語化力の高いBizDevや実装の責任を負うエンジニアに太刀打ちできずに、ものづくりに対するパッション自体も押し込められてしまうと、とても危ない。そこは、僕たちリードメンバーが引き上げていくことが大切だと思っています。(河西)

デザインの民主化は、さまざまな可能性を広げています。その一方で、他の職種とぶつかりあい、つくり手の発言の機会が奪われ、無関心・無関与へと転じてしまわないか…河西さんの言葉には、実務の現場のリアルな焦燥感が滲んでいます。
また昨今では、デザインの民主化を後押しする形でAIもデザイン領域に広がってきています。デザイナーはどうAIに向き合うべきか。河西さんは、こう語りました。
まだまだ民主化されていない領域として、体験に関わるシナリオのプロトタイピングなんかがあるものの、そもそもそこに今、我々デザイナーが関われていなかったりする。だからこそ数字を理解し、思考し、事業レベルからシナリオを提案していくことが、今後の命題だと思うんです。AIはそういったことのトレーニングにも活かせるので、AI相手に反芻を重ね、想像力を鍛えておく。何をつくりたいか以上に、想像力の鍛錬が今後ますます重要になるんじゃないかと思います。(河西)
出力を増やすより前に、思考する。そうして想像力を磨くことが、デザインが民主化された社会でデザインに携わるうえでの責任でもある。そんな覚悟のようにも聞こえました。それは、AIと共に働くこれからの時代を見据える山林さんも同様です。
覚悟を持って「これがいい」と主張できるような知識やスキルを、今以上に身につけていかないといけないんだろうなと思います。AIをパートナーとして使っていくなら、私たちが意味を与え、リードしていかないといけないんだろうなって。(山林)

デザインが多くの人にひらかれたものになりつつあるからこそ、デザイナーはもう一度自らの中にあるデザインへの情熱に耳を傾け、あくなき鍛錬に向き合う必要があるのかもしれません。民主化によって奪われるものがある一方で、広がるフィールドもある──そんな可能性を感じさせるセッションでした。
デザインに愛(AI)は必要なのか?
【登壇者】
・株式会社グッドパッチ クリエイティブディレクター 栃尾行美さん
・株式会社MIMIGURI デザインストラテジスト/リサーチャー 小田裕和さん
デザインにおける「愛(AI)」をテーマとした本セッション。AIが急速に進化するなかで、人はなぜデザインに関わり続けるのか? そこにある「愛」を見つめ直します。
まずは直球の質問、デザインへの愛について。さまざまな場面でデザイン愛を感じる発信をされている栃尾さんの愛は、どこから来ているのでしょうか?
つくったものを喜んでもらえるのが嬉しいんです。喜んでもらえるのがわかっているからこそ、のめり込んでしまう。それは、デザインの力を信頼しているからなのかもしれません。(栃尾)

こういったつくる喜びは、AIの利用の有無によって変わるものなのでしょうか?栃尾さんは、「覚悟」という言葉を用いてこう語りました。
AIの出したものをそのまま出すのは違うと思ってしまうし、たとえ一見良いアウトプットに見えたとしても、自分の仮説と照らし合わせて納得できないと提出するのも嫌なんです。覚悟を持って「これが良いと思っている。だからやらせてください」って言えるものになっているか。AIは覚悟を持てないから、そこを担うのは人間しかいないのかなと。(栃尾)
AIは最適解を出してくれますが、正解がない状況で「これがいい」と信じて差し出すのは、人間だけができることです。そのプロダクトやデザインを愛せるか。何かあったときに責任を持てるか。AIでは担いきれないこの感情や姿勢こそが、人間が創造の場にいる意味だと栃尾さんは言います。
一方、小田さんが愛を込めて語ったのは、つくることの原点にある「問いかけと応答の繰り返し」です。
デザインって終わりがないなと思います。終わらない問答を繰り返し続けること自体が楽しいなって。形にして、反応を見て、また問答して……みたいなことを、ずっと自分起点で繰り返し続けることが、デザイナーという生き方の大切な点だと思っています。(小田)

AIにできることがどれだけ広がっても、どれだけプロセスが省力化されても、自己問答しながら何かを形にしていく楽しさに導かれて没頭する…そんな「デザイン」が、これからも変わらずにあり続けてくれたらと願うセッションでした。
私たちは何と戦っているのか?
【登壇者】
・ファインディ株式会社 デザインマネージャー 向晃弘さん
・KRAFTS&Co.合同会社 デザインディレクター 倉光美和さん
セッション4つ目にして、これまでとは少し毛色の違うテーマが登場。戦う派・向さん vs 戦わない派・倉光さんによる30分一本勝負を通じて見えてきたのは、「自分をどう動かし続けるか?」という切実な問いでした。
まず向さんが明かしたのは、常に仮想敵を必要とするご自身のスタイルへの葛藤。背景にあるのは、誰かとの比較や乗り越えるべき壁の存在だと言います。
常に自分で仮想敵をつくるのが当たり前になっています。本当は戦いたくないけど、No.1になるには戦い続けるしかないし、休んでいる間に置いていかれるのが怖いんです。生を実感するために戦っている、みたいなところもあるかもしれません。(向)

そんな向さんの生き様を、ふたりは『ドラゴンボール』の超サイヤ人にたとえて捉えます。日本一、世界一、そして宇宙一を目指すのだと。
ただ、誰もが戦えるわけではないし、戦わなければいけないわけではありません。特に現代では、働き方に対する理想やスタンスは以前に比べて多様化しています。とはいえ、身体に染みついた働き方を急に変えるのは難しいもの。それでは、向さんのような方がありのままで働き続けるにはどうしたら良いのでしょうか?
なにかきっかけがあれば、超サイヤ人になる人はいるので、そのチャンスメイクをどれだけできるかかなと。周囲に対して超サイヤ人になる道を丁寧につくっていくことで、自分自身もずっと超サイヤ人でいられるかもしれません。(向)
一方の戦わない派・倉光さんも、以前は怒りを抱えながらの仕事で戦っていた時期もあったといいます。その経験から、向さんの「戦う」という言葉の裏にある「より良い状態を目指す」モチベーションに共感を示しつつ、それを戦いとは捉えない視点や、そのエネルギーをつくることに注ぎ込むという切り替えの可能性を提示してくれました。
育休でいったん離脱して復職した時に、「なるようにしかならん」って悟りました。そこからあまり怒りとか、戦うという考え方はなくなって、「なるように精一杯努力しよう」と考えるようになったのかもしれません。(倉光)

誰かの働き方やスタンスに流されるのではなく、少しずつ今の自分にあった環境をつくり、周囲にもスタンスを示していくこと。そんなちょっとした心がけが、自分なりの働き方と上手く向き合うコツかもしれません。
インターネットにおける信頼とは?
【登壇者】
・株式会社アシュアード サービスデザイナー 戸谷慧さん
・ustwo Tokyo プリンシパルデザイナー 中村麻由さん
情報にあふれ、誰を、何を信じるかの判断がますます難しくなっている現代。インターネットを前提としたつながりが増えていくなかで、人と人とはどう信頼を築けば良いのでしょうか?そんな問いを軸にしたセッションが、「Yoitoi Summit 2025」のラストを締めくくります。
まず印象的だったのが、信頼のつくられ方と人と会うことの関係性が変わってきているという視点。戸谷さんは、その変化をこう語ります。
十数年前は、インターネットを通じて新しい出会いがあって、一緒におもしろいことをしたりして、自分の世界が広がる感覚がありました。そこから実際に会って、より親密になることもありましたよね。でも今は、会うというハードルがすごく高くなっている。そのハードルを乗り越えるのは、もう一段難しさが増したような気がします。(戸谷)

時代の変化によっても変わる、信頼のあり方。中村さんは、文化や国の慣習によっても異なる可能性を示しつつ、これからの時代に則したあり方を探ります。
日本は製造業が強かったので、その文脈で培ってきた信頼のつくり方が土台にあると思います。でも技術の進化が早く、不確実性が高い現代では、信頼の指標も変わります。今重要なのは、「うまく一緒に転べるかどうか」だと思うんです。(中村)

製造業で重視されるのは、「ミスをしない」「品質にムラがない」といった正しさや完全さです。しかし失敗と試行錯誤が常態化するなかでは、その過程を共にできる──「一緒に転べる」関係こそが、信頼の新たな基準になりつつあるのかもしれません。
こうした人と人との関わりを語るとき、切っても切れないのがSNSの存在です。戸谷さんは、一切リンクもなく30日で投稿が消えていく仕様の個人サイトで写真や文章を公開しているそうで、その試みを通じて感じたことを共有してくれました。
個人サイトは、じっくり関わってくれる人じゃないと信頼関係が結べない仕組みになっています。ストレスやリスクを最小化するために繋がりを減らすと、信頼という評価からは遠のいていく。この試みを通じて、リスクやストレスと開放性とのバランスというものがあるんだなと思いました。(戸谷)
中村さんもまた、人との関係性を選び取り、自分らしさを出せる場を絞る必要があると語ります。
人と人とのやり取りや信頼をつくっていく過程って、数が増えれば増えるほど薄くなるんじゃないかな。「自分はこういう人間ですよ」と出しやすくするには、数を減らすことも大事だと思うんです。(中村)
インターネットによって誰とでもつながれるようになった現代。そこで必要な信頼とは、間違いながらも進んでいくことそのものを受容できる関係性なのかもしれません。「Yoitoi Summit 2025」で生まれたさまざまな出会いから、そんな新しい信頼の芽が生まれたら…と思いを馳せた最終セッションでした。
今回初の試みとなった「Yoitoi Summit 2025」ですが、Spectrum Tokyoでは今後もなにかしらの形で続けていきたいと思っています。今回はセッションでもさまざまな実験を行ってみましたが、その形もまた少し変わるかもしれません。次回は「良い問い」とどんな形で出会えるのか、是非楽しみにしてください。






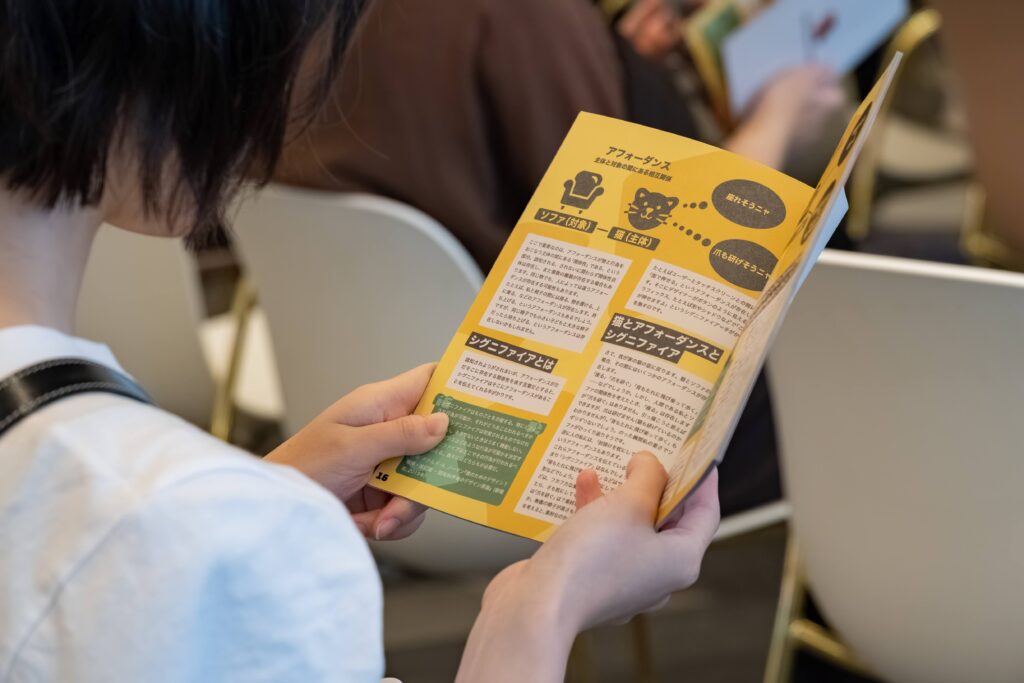

※セッションの様子をもっと楽しみたい方は、こちらからアーカイブをご覧ください。








