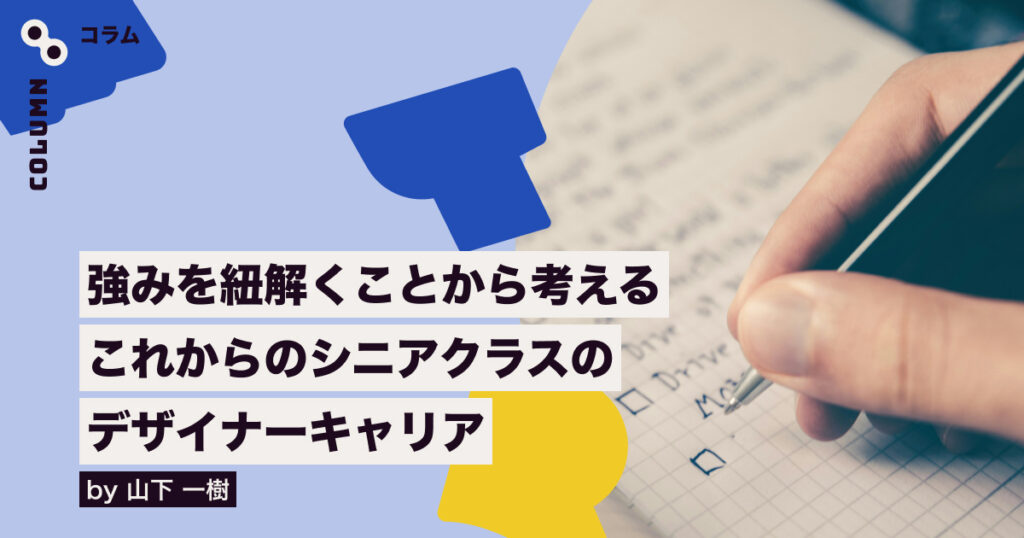人間にしかできない良い問い
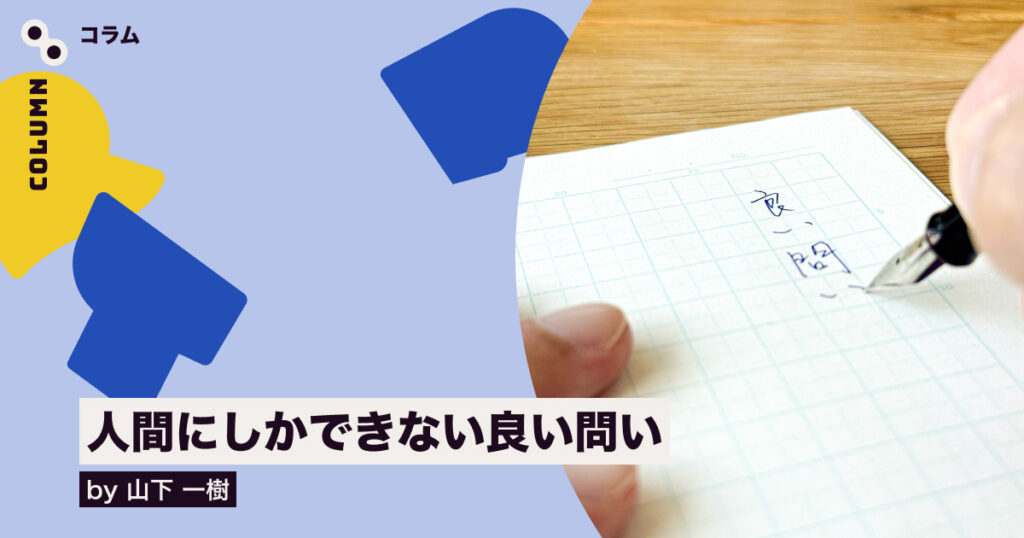
「Why」から始める?
「Why から始めよ」というゴールデンサークル理論は、マーケティング分野でも耳にしたことがある方が多いかもしれません。提供する商品やサービスである「What」を訴求するには、まずは「Why」により提供者が存在する意義や、なぜそれをするのかという起点を明確にすれば、顧客の心を惹きつけ、そこから行動を喚起することができるという考え方です。組織のミッションステートメントにも使命や存在意義が表されており、それが第一義として掲げられる場合が多いです。
「Why」の使い方は異なりますが、トヨタの「なぜなぜ分析」(Why を5回繰り返し、根本原因を分析する方法)しかり、ビジネス界隈では「Why」が思考の標準的なアプローチとして定着している印象があります。
一方で、人間の問いに「Why」はどのように作用するのでしょうか。
「Why」の限界
問いをメインとし、クライアントの気付きを支援するコーチングの現場では「Why(なぜ)」による問いはあまり使われません。その理由のひとつは「Why」で問うことが、単一の理由や原因を探し始め、クライアントの視点が過去へと向かいやすいからです。微妙な言葉の違いですが「なぜそう感じましたか?」よりも「どのあたりでそう感じましたか?」と問う方が、過去に行き過ぎず、実際的な出来事にフォーカスしやすくなります。
「Why」は、トヨタの「なぜなぜ分析」に代表されるように、原因分析や問題の根本を突き止めるには有用な問いです。私たちは成人になるまでの学校教育を通じ「問いには答えがある」「正しい答えを見つけるとマルをもらえる」という経験をしてきました。その経験からか「Why」で問われると無意識に「正解」や納得できる「答え」を探そうとしがちです。
しかし、実社会や人生、人との対話の中では、そもそも「唯一の正解」が存在しない問いや状況が多くあります。こうした「答えのない問い」を本質的に追究し、新たな視点や思考を深めるために「Why から始める」だけでは不十分なケースが多いのです。
「How」で問う
コーチングでは Why に代わって「How(どのように)」という問いが中心です。たとえば「なぜ目標に達しないのか?」と問うのではなく「あなたならどのように目標を捉えていますか?」と問いかけるのです。「How」で問うことで、答えをひとつに絞るのではなく、多様な選択肢や、自分ならできそうなことが自然と想起されるように促します。
さらに、その「How」による気付きやアイデアを他者と共有し合うことで、対話や議論が深まり、視野も広がります。最終的には「今、私には何 (What) ができるのか・何ができないのか」と現状に目を向け、具体的な行動に落とし込むことができるのです。そして、こうした過程から「なぜ (Why) 自分はそれを選ぶのか・なぜこれを目指すのか」という本質的な問いにつながることも少なくありません。
人に内在する「意思」は初めから強いものとは限らず、こうした本質的な「良い問い」によって明らかになっていくものです。
このような対話や内省における「良い問い」は、まず「How」で未来や可能性に目を向け「What」で現状や具体策を整理し、最後に「Why」で本質や動機を問い直します。これは単なる原因分析にとどまらず、答えのない問いに向き合い、クリエイティブな探究と成長を促すための鍵となります。
AI における「問い」の混乱と本質
近年「生成 AI の登場によって問いの力がますます重要になった」という主張をよく耳にします。私自身はこの通説を直感的に理解できませんでした。AI の進化により「課題設定」や「プロンプトリテラシー」といった手法が流布され、多くの人が「問いの立て方」を論じるようになっています。一方で、これらの議論はしばしば混線し「問い」の本質が見えにくくなっているようにも感じられます。
AI に適切な指示を与え、期待するアウトプットを得るための技術として「良い問い」が語られる場面も増えましたが、これは本来の「問い」の意味とはやや異なります。AI 活用の技術や課題設定の方法と、人間本来ができる良い問いを立てることとは、似て非なるものです。 前者は「外部から最適な答えを引き出すための技術」であるのに対し、後者は「自らの内面から新たな意義や可能性を生み出すための営み」です。この二つを混同すると「問い」の本質を見誤ってしまいます。そのため、生成 AI の登場において問いが重要だと語られる背景には、何か見落としている論点があるのではないか、という疑問を持つようになりました。
人間らしい「良い問い」
改めて考えてみると、AI の登場によって変わったのは「答え」や「知識」が持つ価値のほうだと言えます。AI は膨大な情報を瞬時に解析し、正解や過去の事例を簡単に提示できるようになりました。その結果「人間が答えを知っていること・情報にアクセスできること」自体の価値は大きく低下しています。
次なる時代において「自分ならどのように問うか」という、人間だからこそできる問いの立て方のほうが、より重要性を増しているのではないかと考えます。そして、その「人間らしい問い」を生み出すためには、単に知識を活用するだけではなく、自分自身の経験や価値観、内面の葛藤や理想に目を向け、自分らしい「How」を問い続けること、すなわち、内省的な対話の中から問いを紡ぎ出していく姿勢こそが、本質的な良い問いになります。
その人のやり方や生き様に価値があります。その中から湧き上がる「問い」を大切にする。そのプロセス自体が、AI には決して模倣できない、唯一無二の人間性の表現ではないでしょうか。
自分らしい「How」から始める
こうした時代においては、他者の正解や一般論に頼るのではなく「自分ならどのように考えるか」を自ら問い続けます。日々の仕事や人間関係の中で「私ならどう考えるか・どのように取り組むか」を繰り返し問いかけてみてください。そうすることで、単なる知識や答え以上の自分らしさ、本当に大切にしたいことが少しずつ見えてきます。
ぜひ、あなた自身の「How」を大切にしてください。自分にしか見つけられない問い、それを通じて自分自身や他者と真摯に向き合い、新たな意義や可能性を切り拓いていく。それこそが人間にしかできない、最もクリエイティブな営みなのだと思います。
・・・
問いを起点に考え、ディスカッションを繰り広げる新しいタイプのデザインカンファレンス『Yoitoi Summit 2025 powered by Spectrum Tokyo』は2025年7月19日(土)開催!