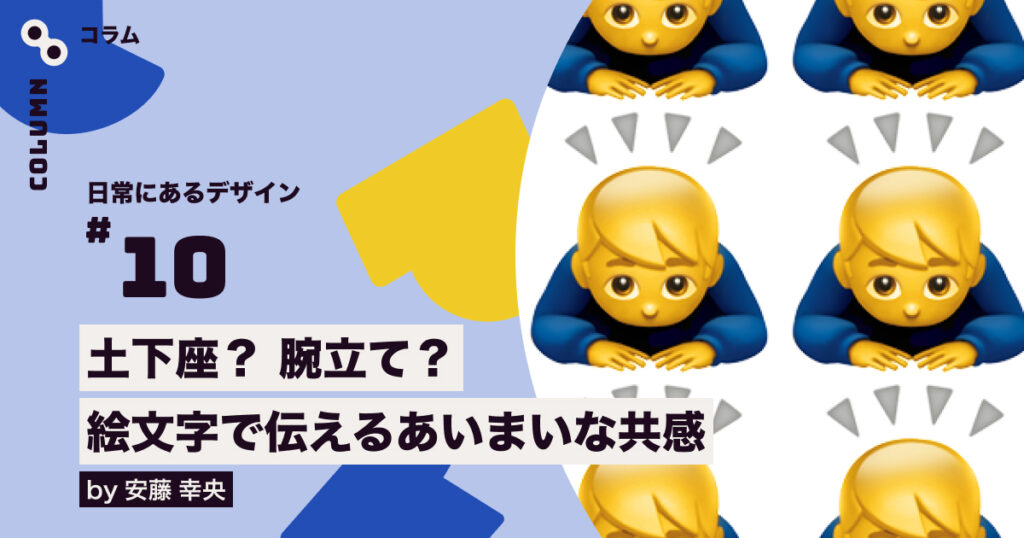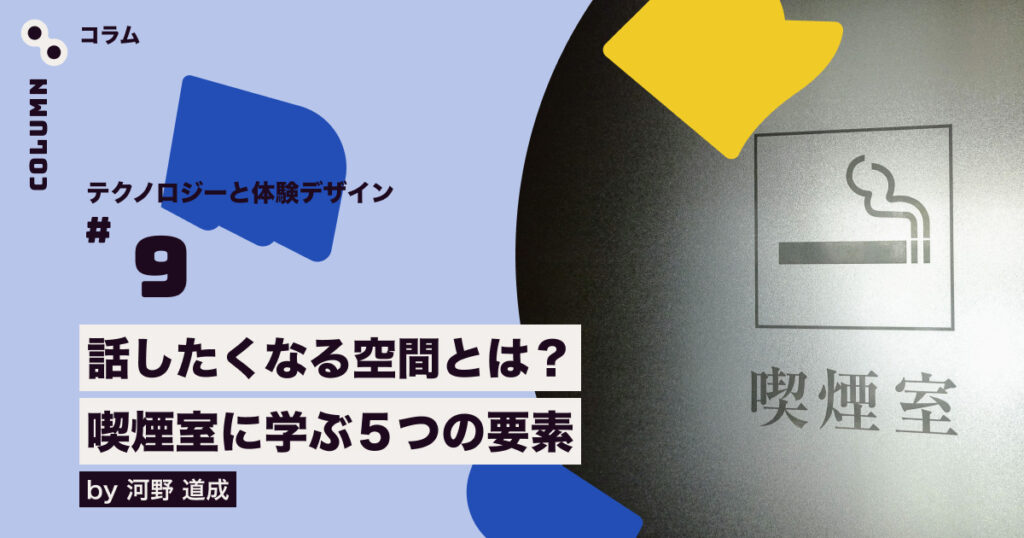最初の体験設計は「授業」だった。小学校教諭からUXデザイナーになって見えたもの
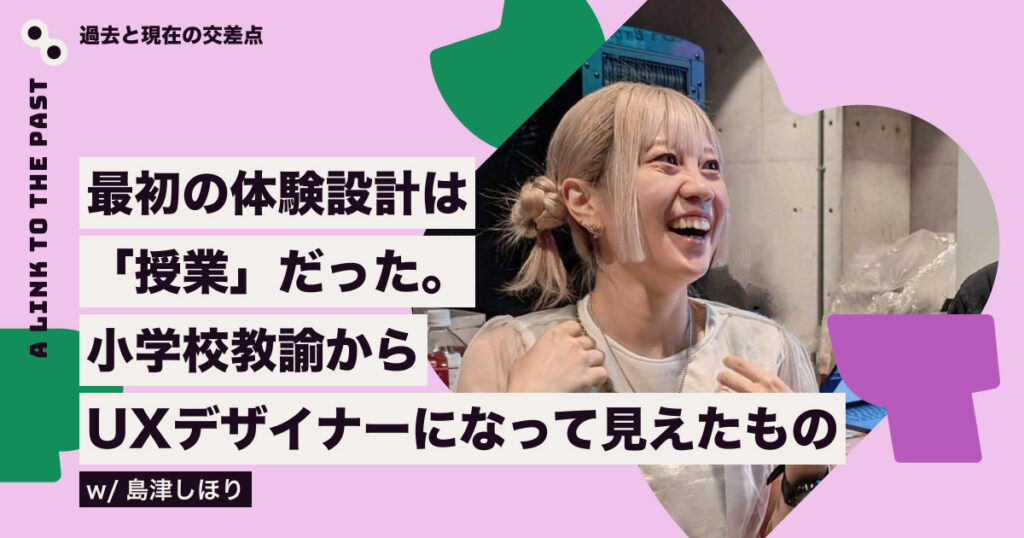
あなたの最初の仕事はなんですか?
ものづくりやデザインに関わっている人でも、最初の仕事が現在と直接つながっているとは限りません。ただ、過去の経験がいまに活きていることも多いのではないでしょうか。
このシリーズでは、「最初のキャリア」がどのように現在の仕事に活かされているのかをたずねていきます。
今回は、株式会社インフキュリオンでデザイナー・プロダクトオーナーとして活躍する島津しほりさんに、最初のキャリアについてお話を伺いました。
島津しほり さん
元・小学校教諭という異色の経歴を持つUXデザイナー/プロダクトオーナー。教育現場で培った観察力とユーザー視点を活かし、現在は貯金アプリ『finbee』を中心に、自社プロダクトやクライアントワークに関わる。問いを大切にしながら、学び続ける姿勢と「胸キュン」をベースにした感性を武器に、日々プロダクトの価値を磨き続けている。
“教える”から“つくる”へ キャリアの転換
━━ 現在はどのようなお仕事をされていますか?
私は現在、貯金アプリ「finbee」のプロダクトオーナー(PO)兼デザイナーとして働いており、勤め始めてから約3年になります。そのほかにも、大手銀行のプロダクトを支援するデザインコンサルの仕事を担当することもあります。
finbee(フィンビー)は、銀行の更新系APIを活用し、ユーザーが設定した貯金ルールに従って、連携した銀行口座から貯金用口座へ自動的に資金を振り替える自動貯金サービスです。少額からでもコツコツと貯金を続けられる習慣をサポートしており、私は金融体験のハードルをなるべく低くし、ポジティブな金融体験ができるようなサービス開発を担当しています。機能改善、新機能の開発、事業全体の改善などが主な業務です。

副業としても複数のプロジェクトにデザイナーとして関わっており、ここ数年はデザインの仕事で生計を立てています。これまでには、デザイン事務所やジョブトレーニングをDXする事業会社、ブロックチェーン系のスタートアップなどに関わってきました。グラフィックからUI、UXデザイン、事業開発まで、さまざまな領域に取り組んできました。
そんな私の最初のキャリアは小学校教諭でした。一見するとデジタルデザインとは遠いように見えますが、振り返るとUXデザインに応用できるスキルや考え方をたくさん得られた環境だったと思います。
UXは教室で磨かれた、1対1の観察から始まった体験設計
━━ 最初の仕事では、どのようなスキルが培われましたか?
私の最初の仕事は、小学校教諭です。1年目は特別支援学級の担任で、4年生3人と1年生1人を受け持っていました。もともと子どもが好きだったこと、そして心理学を学んでいた背景もあり、教師の道を選びました。
特別支援学級では、子どもたち一人ひとりの特性に応じた学習計画を作成し、各教科等の指導を行います。得意な分野では通常学級と交流授業を行うことも多く、状況に応じて柔軟に設計、運用する必要がありました。
このころは、生徒ひとりひとりに合わせて常に授業を改善していくことが求められていました。現在のUXデザインの視点で言えば、ユーザーと1対1で向き合っているような状況です。言葉だけでの意思疎通が難しい生徒もいたため、観察力が非常に鍛えられました。
行動を見て「これは好きなことかもしれない」「これが得意なのかな」と仮説を立て、それを次の授業に反映していく。コンテキスト調査法(いわゆる師匠と弟子インタビュー)に近いかたちで、授業の設計に生徒の声を活かすことも頻繁に行っていました。
授業を構築すること自体が、かなり体験設計に近いものでした。目標を設定し、それに向けてなにをすべきかを逆算する。その繰り返しの中に、いまのPdMやPOに通じるPM的な側面もあったと感じています。
━━ 最初の仕事から現在に引き継いでいる哲学や考え方はありますか?
「共に学ぶ」という姿勢は、当時からずっと大切にしてきました。教師というのは教える仕事でありながら、生徒から学ぶことも非常に多い職業です。
そもそも私が教師を目指した理由のひとつに、「バイアスの少ない子どもの視点から学びたい」という想いがありました。どうすれば子どもたちが楽しみながら学べるかを考えるとき、本人たちの感覚をインプットすることが最も重要だと考えていました。
それは現在の仕事でも同じです。ユーザーから学び、その学びをプロダクトに反映させていくという流れは変わっていません。広い意味で見れば、根っこの考え方はずっと同じままなのかもしれません。

全員が関われる仕組みに込めた想い
━━ 思い出に残っている出来事はありますか?
小学校1年生の担任をしていたとき、生徒たちと一緒に学級目標をつくったことがありました。1年生はまだ自発的に意見を出すのが難しいと思われがちですが、「なんでも言ってみて」「一言でも大丈夫だよ」と声をかけると、意外にもいろいろな意見が出てきたのが印象的でした。
ただ、こういった場面では、なかなか声をあげられない内向的な子もいます。そうした子もきちんと参加できるように、いくつかの選択肢を提示して、その中から選んでもらう方法を取り入れました。
私は「全員が参加できること」をとても大切にしていて、それを実現する仕組みづくりに日々奮闘していたと思います。それぞれの子に合った関わり方があるはずで、それを見つけていくことはいまでも大切にしている考え方です。
━━ 影響を受けた誰かの一言はありますか?
「無知の知」という、ソクラテスが提唱した考え方は、ずっと私の指針になっている言葉のひとつです。これは「自分は、それを知らないことを知っている」という意味で、大学時代に心理学を学んでいたときに出会いました。
当時は人の気持ちがうまくわからないことに悩んでいて、自分でも他の人とは少し違う選択をしがちな傾向があると感じていました。だからこそ、少しでも他人の気持ちを理解したくて心理学を学んでいました。
いま思えば、これはUXデザインの基本的な姿勢にも通じると感じています。教員時代も、生徒のことを「わかったつもり」にならないように気をつけていましたが、現在もユーザーインタビューやユーザーテストの場では、知ったかぶりをせず、素直に耳を傾けるようにしています。
立ち返るたびに思い出すのが、この「無知の知」という言葉です。
“ちゃんとしなきゃ”からの脱却 素直な選択が導いたキャリアの変化
━━ 昔の自分に、なにか伝えたいことはありますか?
いまの自分から伝えたいのは、「素直でいることが大切だよ」ということです。苦手なことから逃げるということではなく、自分の本当の気持ちを基準にして行動すると、自然と前向きになれることに気づきました。気持ちに蓋をしてしまうと、なにをやっても苦しくなってしまうので。
当時は「常識的にはこうあるべき」「先生だからこうしなきゃ」といった思い込みが強く、「ちゃんとしなきゃ!」という気持ちが行動の基準になっていました。その結果、やる・やらないを決めるときに自分の気持ちを後回しにして、後悔することもあったと思います。
私にとっては、いろいろな経験を積んで自信を得ることが、素直になるために必要なプロセスでした。教員としての経験だけでは社会の広さや多様さを知るのが難しいと感じていたので、思い切って教員を辞め、新しい一歩を踏み出せたのはとてもよかったです。
IT業界には全体の最適化が意識された環境が多く、結果として個々人も合理的に動きやすいと感じています。だからこそ自分に合っていて、のびのびと過ごせています。
━━ 島津さん、ありがとうございました!
・・・
いま改めて振り返ってみる初心
誰にでもある最初の仕事。まだなにもわからなかったあの頃に淡々と取り組んでいたことが、いまの仕事につながっていることもあるかもしれません。
これからのことを考えるときこそ、自分の過去を見つめ直してみるのもいいのではないでしょうか? あなたの話も、ぜひ聞かせてください。