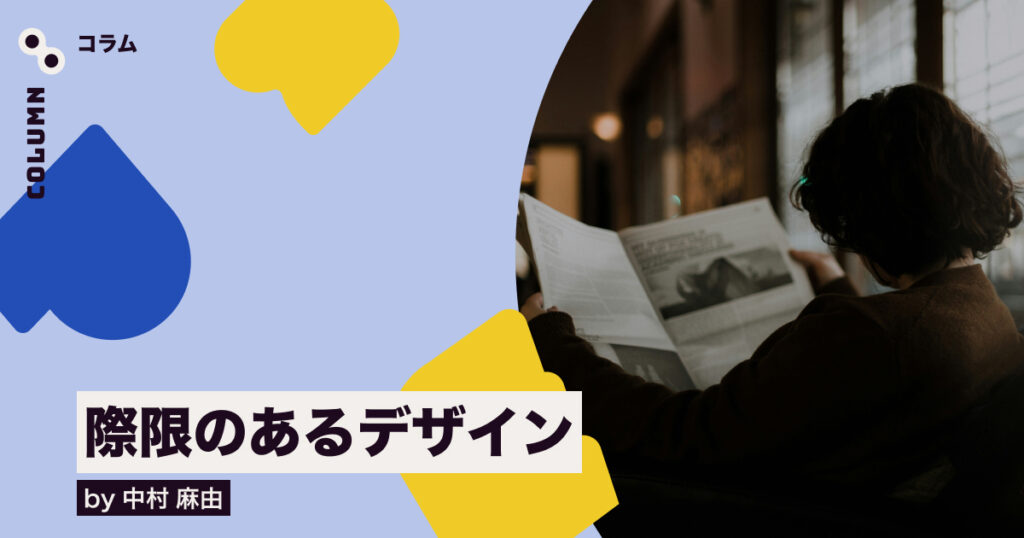デザインをみんなのものに。日本のデザインの脱植民地化を考える
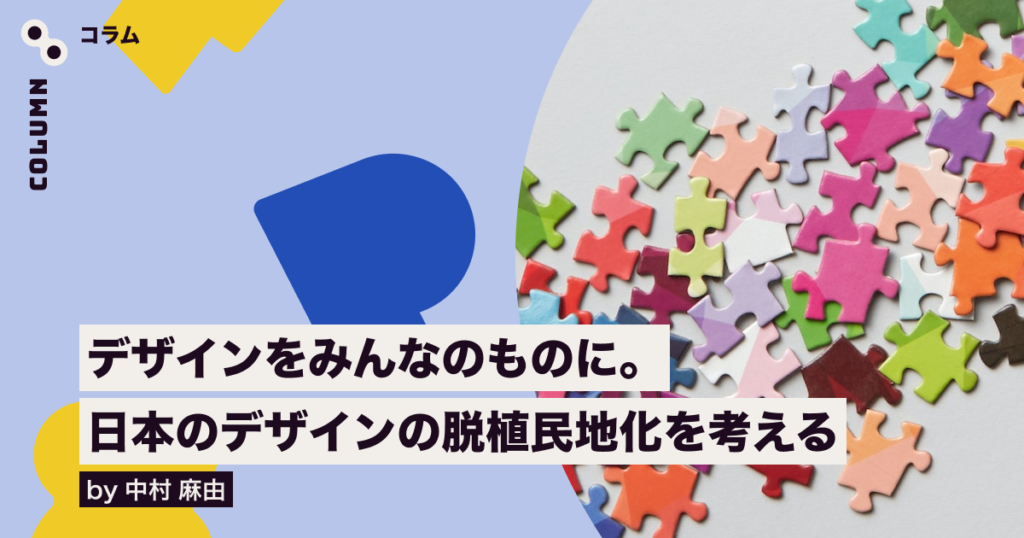
デザインの多様性におけるキートピックのひとつ、「デザインの脱植民地化(Decolonization)」。欧米ではすでに大きく話題になっていますが、日本の文脈で捉えてみるとどうでしょうか。現在の日本のデザインは欧米ベースが主流ですが、それが必ずしも正しく、良いものなのでしょうか。日本や世界のデザインの歴史を振り返り、今後の多様性について一度向き合ってみませんか?
欧米で進む「脱植民地化」
「Decolonization」とはかつて植民地として支配されていた国が独立する、という意味の単語ですが、近年欧米では文化的・社会的側面を含めた広い文脈でこの言葉が出てくるようになっています。
以下はCambridge Online Dictionaryで二番目に出てくる定義です。
“the process of changing something such as a curriculum (= a list of books, ideas, etc. to be studied) in a way that considers the cultural beliefs behind it, for example the belief that European writers, artists, or ideas are better and more important than ones from countries that were colonized (= controlled) by Europe, and that gives more importance to non-European writers, artists, etc.”
背景にある文化的信念を考慮しながら、何か、例えばカリキュラム(=学習のための書籍、思想などのリスト)のようなものを変更するプロセス。文化的信念とは例えば、ヨーロッパの作家や芸術家とその思想は、ヨーロッパに植民地化(=支配)された国のものよりも優れており、より重要であり、ヨーロッパ以外の作家、芸術家よりも重視する、といったようなもの。
この定義を読むと脱植民地化には2つポイントがあるように見えます。
- ヨーロッパが発展させてきたアイデア、価値観「だけ」を優性とする見方、考え方そのものを見直すこと
- 歴史的に抑圧されてきたグループに属する作者、芸術家などの思想、業績にスポットライトを当てること
最近では、欧米諸国にある美術館が過去に他国から持ってきた美術品を返そうとする動きなどのニュースをみなさんも聞いたことがあるのではないでしょうか。
他にも植民地化の過程で失われた、食物の育て方、土地の使い方などの食糧システムに再び注目が集まったり、西洋医学の影であまり日の目を見てこなかった健康促進に関するノウハウを改めて広めるなど、さまざまな分野で脱植民地化の動きが広まっているようです。
デザインを「脱植民地化」する
デザインも他の分野の例に漏れず、主に欧米の価値観を中心に一部の白人男性が形作ってきた経緯があります。彼らの視点と価値観を基になにが「正しい」「良い」デザインかが決まり、それを元にしたカリキュラムが多くのデザイン教育機関で採用されています。さらに言えば、そのデザイン教育を受けること自体にも格差があります。
この不平等な状況を植民地主義の遺産と捉え是正しようと、近年欧米のデザイン業界ではDecolonizing design(デザインの脱植民地化)というフレーズがよく聞かれるようになってきました。
参考:デザインの脱植民地化? デザイナーとしての社会的な役割を見つめ直す。Design Matters 22参加レポート
具体的には、マイノリティのグループに属するデザイナーたちにスポットライトを当ててその考えや手法を広めたり、デザイナーになりたくてもなかなかチャンスが与えられなかった人たちを積極的に支援したりするなどの活動です。私が所属するデザイン会社 ustwoでも、若い才能たち、多様性、インクルージョンを重視するコミュニティと連携してデザインについて学ぶ場を設けたり、社内の活動ではBLM(Black Lives Matter)月間のようないままで注目されていなかったアーティスト、デザイナーなどについてシェアをする活動などを行っています。
参考:ustwo announces global partnership with Where are the Black Designers?
日本の文脈で考えてみる
では、この流れを日本の文脈で考えるとどうでしょうか。
脱植民地化というのは植民地主義によって土地や文化、権利を奪われてきた先住民にルーツを持つ人たちが、現代まで続く不平等を是正しリソースを取り戻すための取り組みです。現在起こっている議論のほとんどが膨大な植民地を持っていたヨーロッパの国々や、移民から始まった歴史をもつアメリカの社会構造に深く根差したものです。
そのため、日本の文脈で「デザインの脱植民地化」を考えるにはまず、歴史や社会構造、その背景にある価値観などを日本のものに置き換えて考える事から始める必要があります。本稿ではまずその手前の一歩として、植民地主義に根ざすかどうかに関わらず、今のデザイン業界の主流になっている「視点」を再考してみたいと思います。
「デザイン」という概念の輸入
日本の近代デザインは、1950年代に欧米から学んだ概念や理論を元に、グラフィックデザインや工業デザインなどの分野で発展してきました。欧米の視点に日本の視点が混ざり合ってきた日本のデザインは、完全に欧米の価値観に染まり切っていないユニークな観点があります。一方、欧米の価値観に倣っていく中で、失われてしまった日本独自の「デザイン」も多々あるでしょう。
たとえば、「日本のデザインはどうしてあんなにゴチャゴチャしているのか?」というテーマはしばしば海外のデザイナーに取り上げられていますが、近代以前の日本のデザインを見てみるとミニマリズムのものも多いように見えます。欧米の価値観を取り入れていく中で、そのようなスタイルは姿を消してしまったのでしょうか。逆にゴチャゴチャしていることはデザインとして良くない、というのは欧米的な価値観なのでしょうか。
「デザイン」という言葉の箱
次に、言葉自体に注目してみます。デザインという単語は、外来語であるがゆえに私たちが認識する言葉の意味が狭いという側面があります。ネイティブがdesignと聞いたとき、「設計」や「計画」といったニュアンスも含め多くの意味を読み取ることに比べ、日本語の「デザイン」は特定の文脈のみに使用されがちです。
その結果、デザインという活動がなにか特別な人たちのために、特別な人たちが行う、特別な活動と捉えられている場合も少なくないでしょう。「デザイナーズ〇〇」といった使われ方が象徴するように、世間的には「(必須ではないけれど、お金をかけて)カッコよくすること」「ちょっと見栄えが良くなればいい」「自分たちの組織には関係ないこと」と距離を置いている人も多いように考えます。必須ではないと認識されているため、予算が少ない場合に真っ先に削られてしまう活動でもあります。しかし、デザインへの投資を最低限の抑えた結果、理想的な体験設計にならず、逆に長期的に見てコストがかかってしまっているケースもあるのではないでしょうか。
また逆に、本来はデザインと言ってもいい活動がそう認識されていないケースもあります。事業企画、オフィス環境や業務規則、行政が行う政策、社会システムなど、デザインの原則や知識が貢献すべき分野はたくさんあります。しかし、クリエイティビティとは無縁だと思われているこういった活動は、既存の慣習の是非が疑われないまま、デザイナーたちが入っていけない領域になってしまっています。
このように、現在の「デザイン」はその言葉の定義の制約そのままに、小さな箱の中から出られないでいるかもしれません。

コミュニティ内のバイアス
次はその箱の中にあるコミュニティについて考えてみます。この業界に限らず、1950年代辺りからの日本の歴史を考えると、社会や経済活動を牽引してきたのは圧倒的に男性が多いでしょう。近年ではもちろん女性のデザイナーも増えてきてはいますが、リーダーポジションの女性の数はまだ少なく、国内のデザインカンファレンスの登壇者もグローバルのイベントに比べて大幅に男性が多いことに気付くと思います。こういった状況は日本に限ったことではありませんが、問題を認識し見直していこうという意思を強く持ち、思想的、組織的リーダー層に多様性を加えていこうとしている国々と、そうではない国々との差は開きつつあります。
また、「女性はマイノリティの中のマジョリティ」とよく言われるように、これは性別だけの話にとどまりません。現在のデザインは健常者の視点がほとんどですし、日本語が話せない人向けのデザイン、左利きの人向けのデザイン、LGBTQの人たち、人種的にマイノリティな人たちなど、日本のデザイン業界にいるマジョリティが取り上げてこなかった視点はまだたくさんあります。少しだけ脱植民地化の文脈に戻ると、日本がいままで「支配」した過去がある文化、社会、そのコミュニティに属する人たちに対してフェアなデザイン業界になっているでしょうか。
グローバルデザインコミュニティの一員としての日本
最後にグローバルデザインコミュニティとの関係についても考えてみたいと思います。すでに触れたように、現代のデザイン理論は主に欧米の視点になっています。我々が「グローバル」と言ったとき、ほとんどの場合それは欧米を指すのではないでしょうか。しかし本当の「グローバル」はもっと広いはずです。
The Next Billion Usersの著者、Payal Arora氏は欧米以外の地域を「遅れている」と捉えるのではなく、「次世代の10億人のユーザー」としてイノベーションの中心に据えるべきだと主張します。他の国々が当然のように欧米と同じ道筋を辿るだろうというのはおごった考えであり、他の地域の価値観や文化にもっと目を向けることで、人類全体としてイノベーションは加速する、という考えです。
この先、必ずしも欧米社会の価値観だけが注目されるデザインコミュニティではなくなった場合、私たち日本のデザイナーはどんな関わり方ができるでしょうか。多様性のある社会では「違うこと」は大きな強みです。バックグラウンドが違う、価値観が違う人々がそれぞれの視点を持ち寄って一緒に問題に向き合えることは、イノベーションの大きな原動力になるからです。英語圏から輸入されてきた「デザイン」という概念の枠を大きく超えて、日本が長い歴史と社会の中で培ってきたデザインのノウハウや知恵はグローバルコミュニティでも大きなインスピレーションを与えることができると思います。
最後に、デザイナー個人は具体的にどんなことができるのか、いくつか提案します。
まずは国内でのデザインの視点を広げるためにできることです。たとえば、1950年代以前から続く日本の文化には、どのような「デザイン」があるでしょうか。また、「デザイン」という名前がついていなくても、周りにデザインをしている人はいませんか? そうした人たちとデザインについて語り合うことで、周りの人たちのデザイナーのイメージを広げることができるかも知れません。また、自分とは違う属性を持つ、いままでスポットライトが当たってこなかった人たちの「デザイン」を学んでみることもひとつの方法ですし、デザイナーの採用に関わっている人たちは、自分たちのチームの「視点」が多様であるかどうか、一度意識してみてもいいかもしれません。
また、グローバルデザインコミュニティに参加することも考えてみましょう。欧米圏以外のデザインについて調べてみたり、デザインカンファレンスに参加してみたりするのはいかがでしょうか。日本から自分たちのデザインの取り組みを世界に発信することも大切です。もしハードルが高ければ、国内で開催されている国際的なデザインコミュニティのイベントに参加してみることもオススメです。
「デザインはもっとさまざまな人が関わるべき活動」「デザインはもっと民主化されるべき」── みなさんはどう思いますか? ぜひ感じたこと、考えたことなどお聞かせください!
・・・
コラム読んでの感想やご意見はぜひソーシャルメディアで。SNSのハッシュタグは #spectrumtokyo です。下記のシェアボタンで是非感想をお寄せください↓