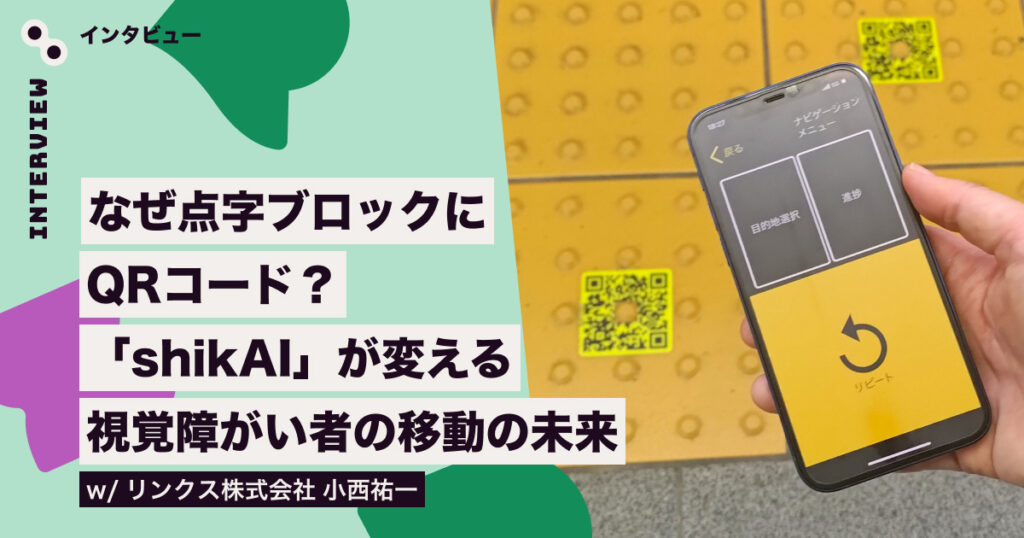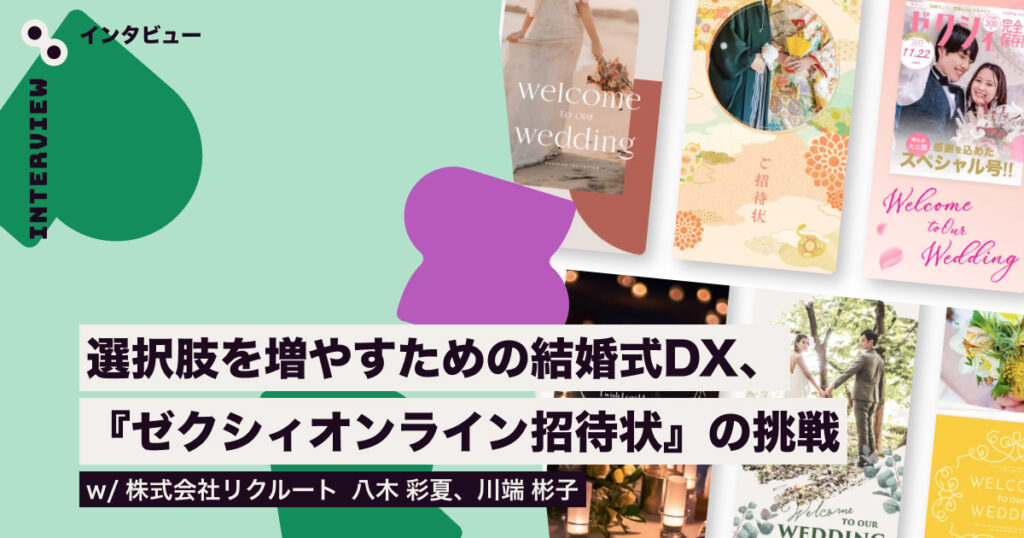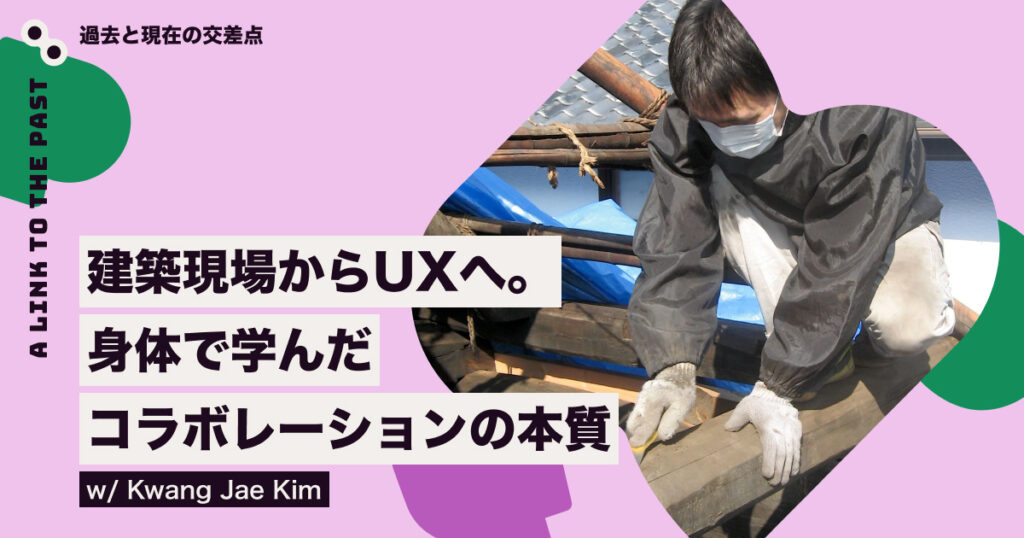デンマークと日本をつなぐayanomimiから学ぶ、異文化で企業コラボレーションを実現させる秘訣

Managing director & Founder of ayanomimi
福祉、医療分野をはじめとしたインフラのデジタル化が進むデンマークは、あらゆるデザイン分野で世界的にモデルケースとして注目されています。
時代とともに変化する社会ニーズに応えるために、国を越えた企業コラボレーションによって新たな価値創出が期待されていますが、それを生み出すプロセスにおける企業間の文化的なコミュニケーションギャップの解消が不可欠です。
今回は「文化の架け橋」として日本とデンマークの企業同士のポテンシャルを活かしたビジネスコンサルティングと企画プロデュースをおこなう、ayanomimi代表の岡村 彩さんにお話を聞きました。
北欧と日本をつなぐコミュニケーター
── 本日はよろしくお願いします。ayanomimi ではどのような仕事をされているのですか?
岡村:ayanomimi はデンマークと日本の企業間の特性を生かしたグローバルな企画を提案するコンサルティング会社です。コミュニケーターとして言葉の通訳だけではなく、ビジネスの背景や習慣、価値観の違いから生まれる「?」を減らし、デザイン、ライフスタイル、イノベーションの分野で共創構造が生まれるプロセスをサポートしています。
私は大学院の在学中にCopenhagen Business School (CBS) に通いながら起業して今年で13年目になります。当時からずっと日本とデンマークをどうやってつなげたらもっとビジネスとして経済的な価値を生み出すか、どのように歩み寄れば前向きに両者の共同開発プロセスを導けるか、ということに興味がありました。
私は日本人の両親を持ちながらもデンマークの教育を受けてきたバックグラウンドを活かし、コミュニケーターとしてデンマークと日本の企業間のコラボレーションの可能性を広げることを目指しています。
── デンマークの教育はレベルが高いとよく耳にしますね。
岡村:そうですね。私自身、パスポートは日本のものですし、日本語で考えてる方が楽だと感じるほど日本人なのですが、生まれ育ちはデンマークなので考え方や思想は現地の学校教育に大きく影響を受けていますね。
振り返ってみると、一度も日本人であることによって悲しい思いをしたことがないので「良い環境だったな」と感じています。いじめが無いわけではないので、私の周りが特に良かったのかもしれません。
これは幼稚園の時のエピソードです。私が3歳ぐらいの時、家では日本語だったのとシャイな性格だったため幼稚園では静かでした。当時、私はデンマーク語でのコミュニケーションが苦手なことに悩んでいたのですが、ある日「なぜデンマーク語で話さないの?」と同級生に聞かれてドキッとしました。
しかし、先生や周りの大人は「Ayaは日本語が話せるから、他の人ができないことができているんだよ。デンマーク語は君たちが教えてあげてね。」と他の園児に説明してくれたポジティブなフォローが心に残っています。
「教育レベルが高い」か? という質問への答えとしては、数値化できる教育レベルについては日本のほうが高いと思います。ただこのエピソードのように個人のできることを「褒めて伸ばす」教育方針はデンマークでは一般的です。個人の自信につながる良い環境だと思います。
このようにデンマークの教育現場で浸透している「できないことよりできること尊重し、異なるもの同士で助け合う文化」がビジネスシーンや社会基盤にも根付いているように感じています。
── デンマークと日本の企業間コラボレーションではどのような分野が多いのですか?
岡村:いままで80ほどのデンマーク×日本の大小さまざまなプロジェクトを斡旋してきました。最初のうちは、デンマークの企業が日本に進出する際の支援が多く、パートナーの開拓や資料翻訳による調査のサポートなど地盤固めを一緒に計画し伴走することが主体でした。
基本的に北欧と日本企業のコラボレーションという話はオシャレな家具や機能美を持った工業製品などインダストリアル方面でのイメージが強いと思います。しかし、最近の企業同士の文化交流ではデジタルの分野が増えており、ライフスタイルや教育など福祉などの領域に広がりを見せています。

デンマークで日本企業のコラボレーションが加速している理由
── デジタル領域というのは具体的にどんな企業が参入しているのでしょう?
岡村:長く交流が続いている分野として医療や福祉が印象的ですね。福祉ロボットなどのニッチな研究や運用テストが共同開発されています。デンマークでは日本やヨーロッパ各国と比較しても社会的なITインフラの整備やデジタル化が進んでいます。
特にフュン島のオーデンセン市という地域ではいまでも多くの日本企業が参入しています。オーデンセン市は人口20万人と東京都台東区と同じくらいの人口です。県には及ばない小ささなので、日本で実施しにくいことも現実的なラインでシミュレーションができ、データを取ることができます。それは「行政のデジタル化」などスケールの大きなテーマでも有効なプロセスなので「デンマークのいろいろな先行事例を見たい」と、フィールドリサーチをおこなう企業が増えていますね。
最近のトピックとしては、富士フィルムの取り組みのインパクトが大きいです。コペンハーゲンの北のヒルロッドという街に拠点を置きバイオ医薬品の製造を行う予定です。現地で450人を雇用するというかなり大規模な取り組みです。
個人的な所感でもありますが、デンマークはデジタルの基盤が整ってることに加えて、政治や宗教にもニュートラルな国柄なので、プロジェクトの市場テストの際にリスクとなる過激な意見対立やデータとしてのノイズが少ないという面もあると考えています。
── 新しいチャレンジをする土壌がデンマークではかなり整っているんですね。
岡村:そうですね、仮にニッチな分野の企業同士の協業でもスピーディなプロトタイプやテストマーケティングを通して世界市場を狙える可能性が出てきます。これはスケールを望みやすい構成なので、非常に期待できます。
一方で問題もあります。ニッチな分野ほどグローバル人材としてのコミュニケーターが不足していることから、パートナーシップを築くにあたって細かなニュアンスや文化性の違いでプロジェクトの企画にスピードが出なかったり、必要な現地でのネットワーキングが滞ったりすることが課題となっています。

国を越えた企業同士のコラボレーション課題に向き合う
── なるほど、ここで「文化の架け橋」としてコミュニケーションのデザインが必要なのですね
岡村:そうですね、私のやっている仕事はデンマークと日本の異文化性を踏まえた上でビジネスコミュニケーションをデザインすることでもありますし、コラボレーション企画の編集・翻訳のようなことだと考えています。
最近の具体例として、無印良品との仕事が印象的でした。無印良品は2020年にデンマークの首都コペンハーゲンにある老舗デパートILLUMに旗艦店となる「MUJI ILLUM Copenhagen」をオープンしました。無印良品はデンマーク人も大好きな日本のブランドのひとつで、理念である素材へのこだわりや合理的な生産プロセスなど含めて評価の高い企業です。
無印良品はデンマークでは初の出店だったので、担当の方は現地でのビジネス計画やネットワークづくりにかなり悩んでいたそうです。それらの課題に対して現地を知るパートナーとして伴走させていただきました。こういった日本企業からの相談は非常に多いです。
他の例としては、先程もご紹介した富士フィルムのように現地スタッフを雇用するケース、または日本から責任者が現地に派遣されるケースです。ビジネスの現場では日常的に起こる文化の違いに戸惑う人が多いので、文化について学ぶ機会やコミュニケーションのサポートはとても重要です。
複数の国をまたぐビジネスでは微妙なニュアンスで指示内容や期待値のズレが生じることがよくあります。このような場合は単純な言語の通訳で終えるのではなく、お互いの文化的背景を読み、コラボレーション企画の編集・翻訳をしなくてはなりません。
── 私たちの普段の仕事のシーンでも非常に身に覚えのある話ですね。
岡村:はい、あるあるですね。私もそういう現場をよく見てきました。でも、それぞれに生まれ育ってきた環境や学んできた習慣があるので、他国のコミュニケーションスタイルを完全に理解することは難しいと思います。それに「日本人は話が冗長で、なぜか結論から話さない」などと片方の文化性を揶揄したり、どちらかの資料作りのフォーマットに最適化するのもフェアではないと思うんですね。
今後はデンマークと日本のどちらか片方のコミュニケーションスタイルに無理矢理合わせるのではなく、もっとコミュニケーションのデザインパターンを増やすことが必要です。
デンマークと日本の企業同士の強みを活かして新しい価値を生み出すプロセスを支援し、お互いがわくわくするようなコラボレーションを実現したいです。
── こういった役割は岡村さんのようにデンマークの教育を受けていないと難しいのでしょうか。
岡村:デンマークの教育を受ける必要はないと思いますが、言葉や知識だけではなくビジネスの背景にある「ロジック」を理解する必要はありますね。企業や個人がなにをモチベーションにして動いているかを理解することが大切です。そのためにはいろいろな立場の人と実際に会ってお話しをしたり彼らの経験について聞くことが大事だと思います。
その他には文化的共通点に注目することも重要です。そこでデンマークでも日本でもBtoBの勉強会やイベントを開催しています。

共通性を見出して強みに変えていく
── デンマークと日本のビジネスパーソンの共通点はどういったところでしょう?
岡村:国民性というと包括的すぎるかもしれませんが、根底的な思想の面で謙虚な人が多かったり穏やかで協調性の高い人が多い印象ですね。誰かを出し抜いてまでも競争の優位性に立ちたいという性格の人は少ないし、そういう人を育てる環境もあまりないです。たとえば、デンマークの学校では成績表がない学校も増えてきています。
組織でうまくやっていこうとする意識や、自分ができないことをできる者同士でお互い補い合おうとするところなど、そういった謙虚な感覚は日本人とデンマーク人でつながるところがあると思うんですよ。
一方でこういった気質からロールモデルになりえるような飛び抜けたプレイヤーが生まれにくいことや、合議制が悪い形ではたらき、物事が保守的な方向で動いてしまいがちな点も似ています。協調性があるところを強みに変えていければ良いですが、この点でも推進力が求められますね。
── 同じようなルーツを持ちながらもデンマークは政府と市民の連携がスピーディな印象がありますね。
岡村:実はデンマークでは行政に対する市民からの信頼度が非常に高いんです。例えば民間企業には個人データを預けたくないけど、政府がデジタル化を推進するならデータを安心して預けるという人は多いです。お年寄りから若い人まで政治や社会に対する関心度が高いこともありますが、政府と市民が相互で頼り合い、果たすべき義務を強く認識しているのかもしれません。
また、デンマーク政府は専任のインハウスデザイナーを雇用しています。必要であれば⺠間のデザインエイジェンシーを起用します。これは政府と市⺠がデザインに対してとても重要性を感じていることを示しています。デザイナーは政府の広報物を作成するのですが専門的な視点から市⺠と行政の間のコミュニケーション全般を設計します。透明性のあるコミュニケーションこそが政府への信頼につながり、市⺠の社会への参加にもつながるためデザイナーの役割は重要です。

イノベーティブな企業連携を生み出す「頼り合う・委ね合う」文化
── つまりデンマークの国民性として、良い意味で頼り慣れているということでしょうか。
岡村:そうですね。企業間プロジェクトの連携の際もその文化が良い方向にはたらいていると思います。デンマークは教育的な側面からそのような文化性を育みやすい土壌ですが、これらの法則性は私が仕事で企業同士のコラボレーションを推進する上でも気に留めています。
先程の話にも出ましたが、これは政府と市民の関係性でも見られます。政府が宣言したから特定のルールやガイドラインが起用されて従うとかではなく「じゃあこの地域を良くするにはどうしたいか」を市民全員で考えます。市民は意見をいえるチャンスがあるのだからと喜んで議論に参加しています。
── 日本はガイドラインやルール作りから始まる傾向が強いように思いますね。
岡村:たしかにそうかもしれませんね。すでに体験されたかもしれませんが、街中の公共交通機関の標識が少なかったり、いたる所の施設や設備で説明がなかったりしませんでしたか? 日本から来訪した方々は情報量の差に驚くかもしれませんね。
私も日本に行った際は情報量の多さに毎回圧倒されます。ですが同時にたくさんの情報が工夫されてまとめられているなと感じますし、ほぼ時刻通りに到着する地下鉄などのサービスの精度にも驚きます。デンマークは普通に、地下鉄が止まって動かなくなることも全然あります。
デンマーク人の国民性として、トラブルがあってもサービスに完璧は求めず「しかたないよね」と自分たちで解決方法を探すような傾向があります。わからなかったら誰かに聞けばいいし、困ったら誰かに頼れば良いという考え方の人が多いんです。たとえば、私たちの居るこのシェアオフィスでも似たような現象が起こっています。張り紙や注意書きは控えめで、備品の場所や施設の使い方などは元からいる利用者に聞いて把握しています。
── 実は、このオフィスがすごく気になっていました!入居されている方を拝見するとかなり年齢層が幅広いように見えますね?
岡村:そうなんですよ。セカンドキャリアで個人事業を立ち上げた人とか、40歳後半、50代などが一番多いですね。デンマークにもさまざまなタイプのコワーキングスペースがあるので、以前はちょっと違う感じのインキュベーションオフィスみたいなところにいたんですが、いまはここが落ち着いていて心地よく感じています。
互助的な文化だからこそ仕事の相談でストーリーやコンテンツについての壁打ちを快く引き受けてくれたり、彼らの豊富な経験からアドバイスをもらえたりすることが嬉しいですね。シェアキッチンでは決まった時間にヘルシーなランチメニューが提供されますし、自由に設備が利用できます。特別なルールは存在しませんがいつもきれいな状態です。

── まさに「委ね合える」文化だからこそ新たなチャレンジを行える素敵な環境ですね!
岡村:ありがとうございます。私の場合はバックグラウンドを活かしてデンマークと日本のプロジェクトにおける「文化の架け橋」となってますが、両国の興味関心は市場とともに当然と変化していきます。なので、コミュニケーターとして日々認識をアップデートすることにも努めています。
こういった活動ができることは、もちろんデンマークの社会性や文化性に共感をしてくださる日本企業のパートナーや、シェアオフィスのルームメイトのおかげでもあります。
私のように国際間の企業コラボレーションやブランディングを推進するコミュニケーターはまだまだ少ないかもしれませんが、今後そのような方面で活躍する方にとってデンマーク的な文化のメソドロジーやayanomimiの取り組みが参考になれば幸いです。
──岡村さん、ありがとうございました!
取材協力
ayanomimi:https://ayanomimi.com/ja/