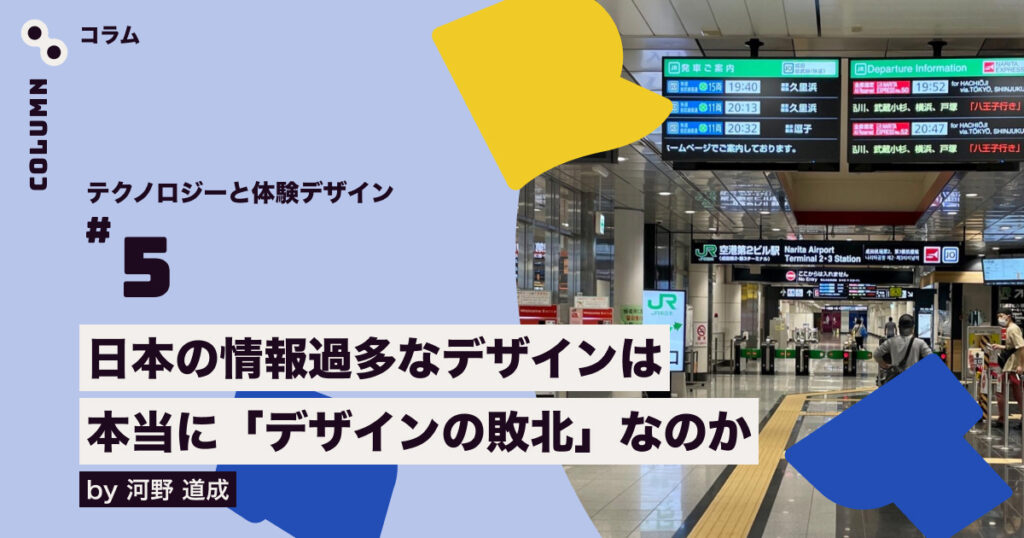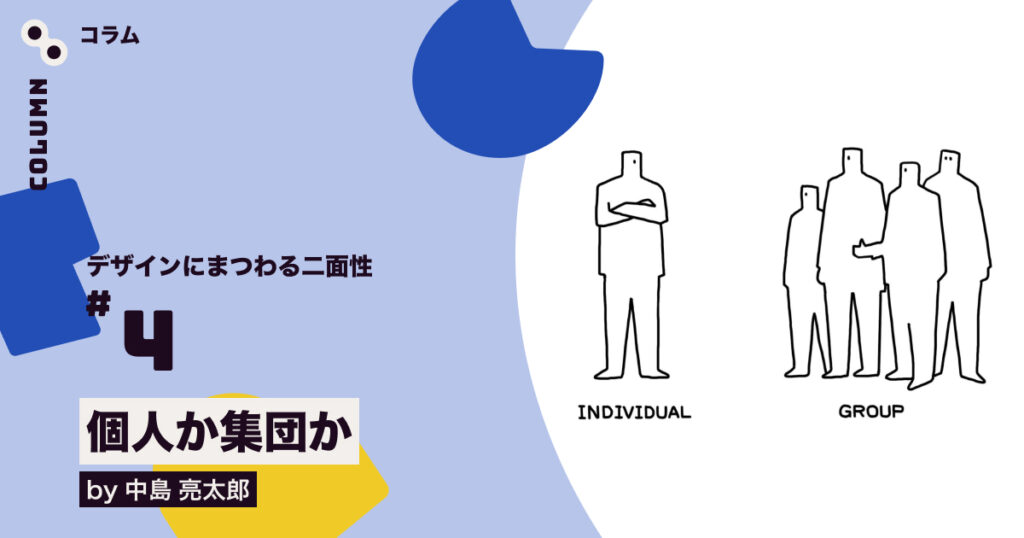サービス体験におけるウェルビーイングは測れるのか
Designing Well / ウェルビーイングをデザインする #2

「目標や指標において、経済的な生産性を測定するのではなく、代わりにウェルビーイングを測定した方が良いのではないか。」ブロックチェーンを用いた人工知能基盤「SingularityNET」のファウンダーであり認知科学者、そしてAI研究者でもあるBen Goertzelはこちらの記事でこのように書いています。生産性が高いだけのプロダクトに投資するのではなく、ウェルビーイングを高める製品やサービスにリソースを割り当てる方がいいのではないかという提案です。
経済生産性はでたらめ(Voo-Doo)であるとする彼の主張には一理あるように感じます。生産性の概念はもっともらしく聞こえるものの、実際のところ業界や業種、企業のステージによって生産の概念は異なるものであり、彼の記事で考察されているように単純なお金の尺度というものは存在しません。
彼の課題意識自体は私も強く共感しています。企業のKPIやOKRに「ユーザーのウェルビーイング」という概念がすっぽり抜け落ちていていることが多いように感じているからです。輝かしいビジョンやミッションは、ユーザーの幸せや社会の発展を願うものであるにもかかわらず、KPIは経済的な数値のみを日々測定しているケースが多いのではないでしょうか。
ウェルビーイングの測定方法とデータの信憑性
Goertzel氏はプロダクトが与えるウェルビーイングの測定方法として次のようなやり方を提案しています。
- 無作為に抽出した人に対し複合的な幸福度の調査を行う
- サービス購入者にも同様の測定をする
- 無作為対象者とサービス対象者のデータセットが比較できることで、そのサービスによる幸福度の増減についての統計的に合理的な推論を行うことができる
Goertzel氏が提唱しているこのウェルビーイングの測定の手法は理屈上では理解できますが、「無作為なリクルーティング」の時点でなかなか恣意的な判断が入りそうです。また「そのプロダクトによってウェルビーイング度が上がったのか」あるいは「ウェルビーイング度が高い人に受け入れられるプロダクトなのか」の判断が難しいなど、現実的には実行にさまざまな課題はあるように思えます。
Goertzel氏は記事の中で多様な幸福の調査方法について言及していますが、イェール大学の心理学教授のLaurie Santos教授は、いろいろある測定方法の中でも「あなたはどれくらい幸せですか?」とストレートに尋ねるシンプルなアプローチは有効な手段のひとつだとしています。「あなたは、今どれくらい人生が良い状態だと思いますか。100点満点で何点くらいか選んでください。」と尋ねるこの手法は、博報堂が実施した大規模なウェルビーイングのリサーチでも用いられたやり方です。筆者が運営するサービス「Nesto」でも定期的にユーザーの満足度調査を行っており、同様の設問でユーザーのウェルビーイング度数を測るということを2022年3月から実施しています。
調査を行うことでユーザーのウェルビーイングの参考値はできますが、データの捉え方は難しいと感じています。喜ばしい結果として、Nestoユーザーのウェルビーイングの点数は博報堂の国民調査と比較すると良い数値となっており、利用期間が長いほど点数が向上するということもわかっています。しかし我々のサービスが人々のウェルビーイングに貢献していると思いたいところではありますが、サービスの性質上、元からウェルビーイングに感度が高い人たちが集まっていたり、その感度が高い人ほど離脱しなかったりすることも要因としてあるとも考えられます。
人のウェルビーイングの要因は複雑に絡み合っているのです。たとえ私たちが実施している調査の中でスコアが向上したとしても、私たちのサービスのおかげだと早急に結論付けるのは傲慢であると思います。

サービスのユーザー体験は幸福度を向上させるのか
では測定する意味がないのではないかと言われると、測定するということ自体にも意義がある実感があります。なぜなら定量的に自分たちのユーザーのウェルビーイングに耳を傾け続けることができるからです。仮にスコアが著しく変わることがあれば、ユーザーになにかしらの変化があったのではと気づくことができます。スコアの変化は自分たちのサービスが要因かもしれないし、外部要因かもしれない。しかし、ユーザーの状態に思いを馳せるということが測定という行為から実現できます。
これは自分たちがデザインしている体験の外に思いを馳せるということでもあります。ユーザーがプロダクトによって作業が効率化できたとしても、それが果たしてユーザーのウェルビーイングにつながっているのでしょうか? サービスを通じユーザーに短期的な快楽を提供できていたとして、果たしてそれはユーザーをしあわせにできているのでしょうか?
ビジネスゴールやKPIとの矛盾が出る局面もあるとは思います。しかし、ユーザーのウェルビーイングとビジネスゴールのトレードオフを意識することなく、ビジネスゴールのみに注力してしまっているケースがまだまだ多いようです。ビジネスをとるのかウェルビーイングをとるのかの自覚的な取捨選択は、ユーザーのウェルビーイングに意識を向けるところから始まるのではないでしょうか。
ユーザーのウェルビーイングの把握とは途方もない話です。自分たちのサービスが持つ影響の責任をより一層考えることにもなります。私たちNestoも測定方法から分析方法まで、まだまだ最適解を見出しているとは言い難いと感じています。ぜひみなさんの取り組みもぜひ教えてください。
写真提供: 本永創太