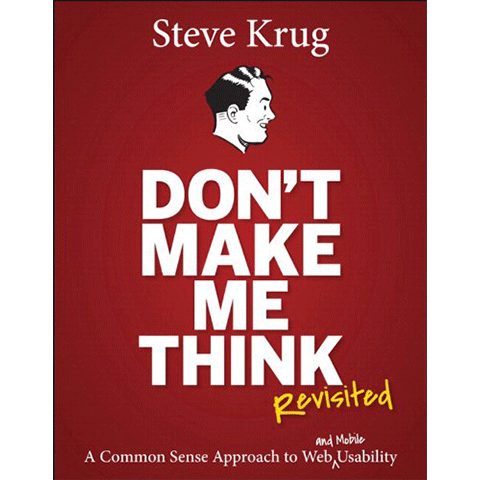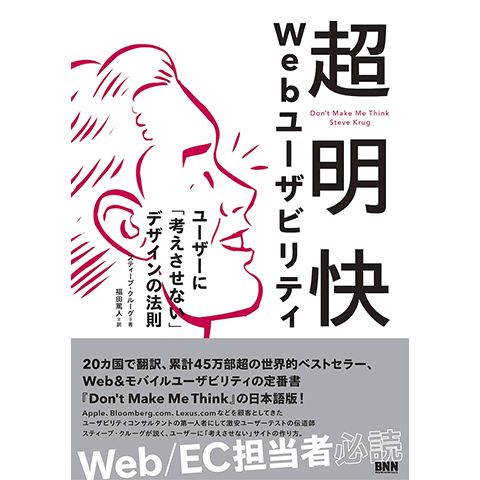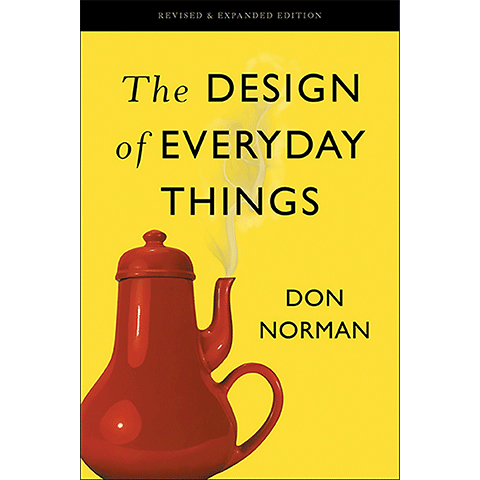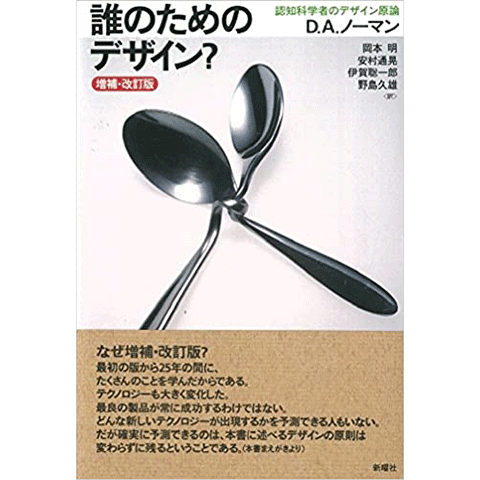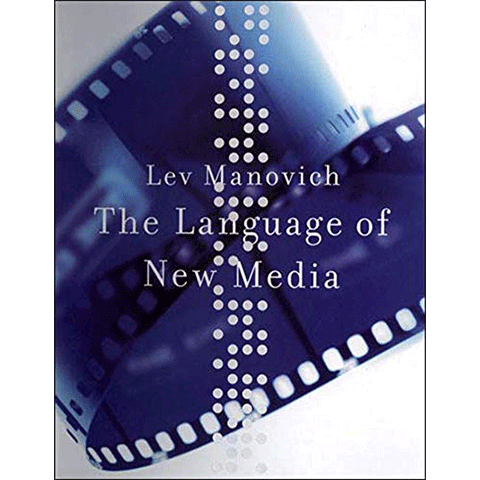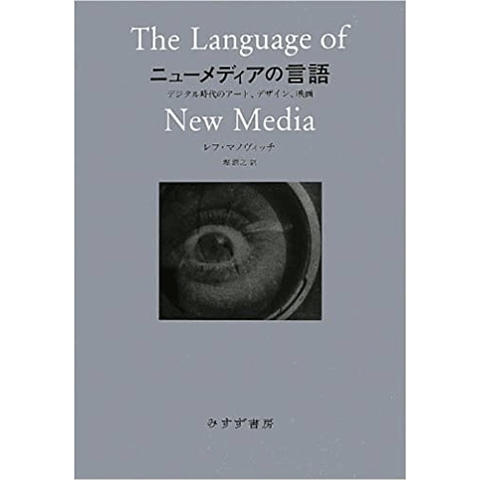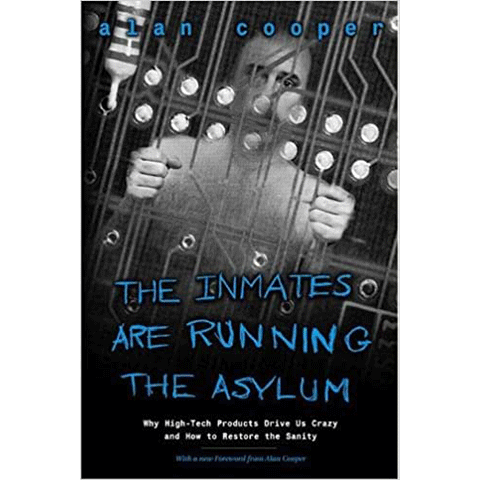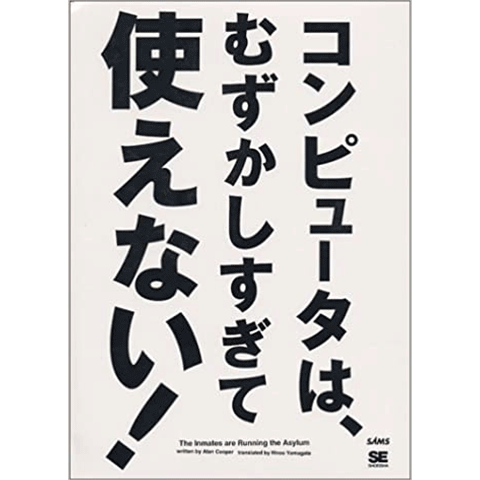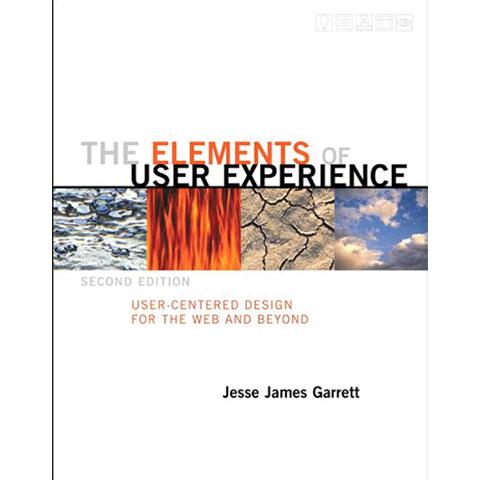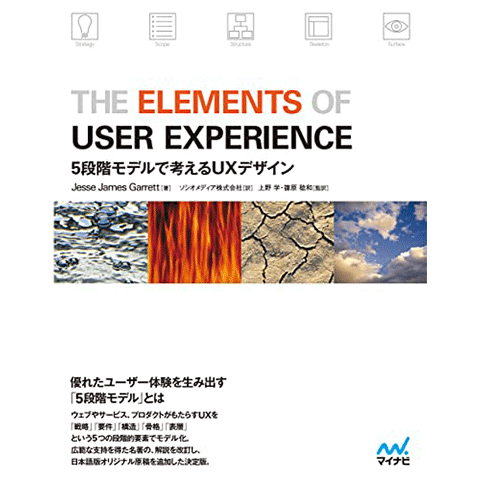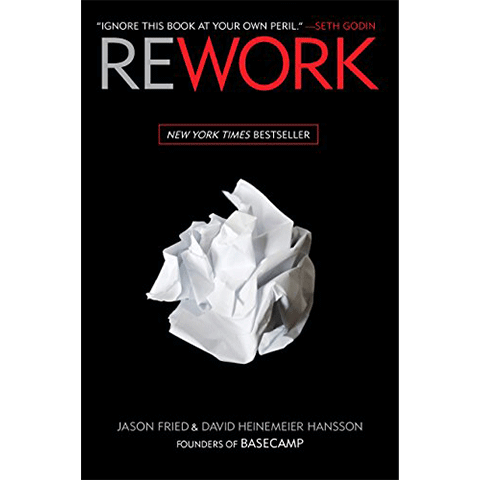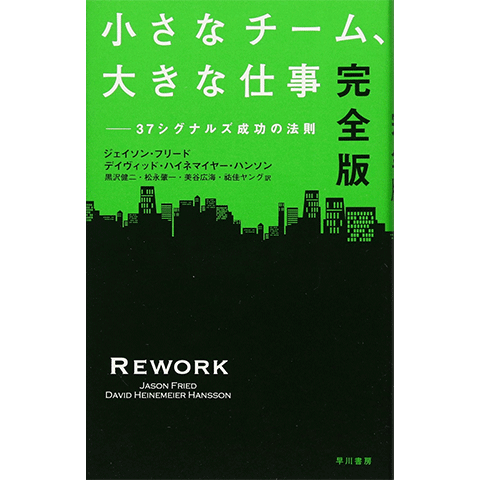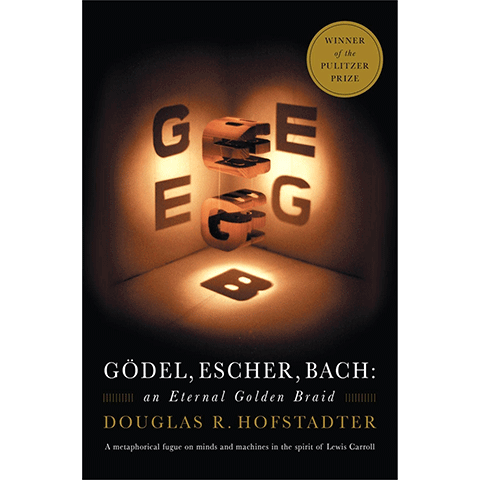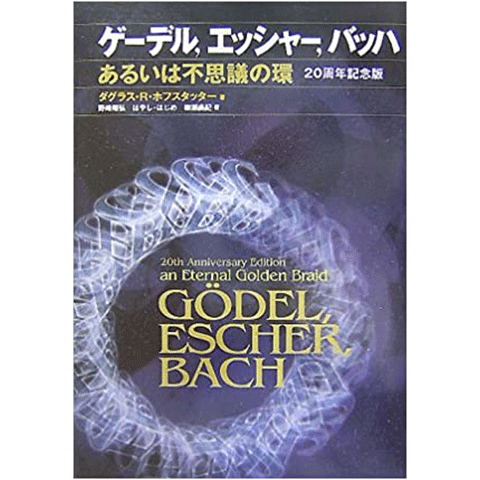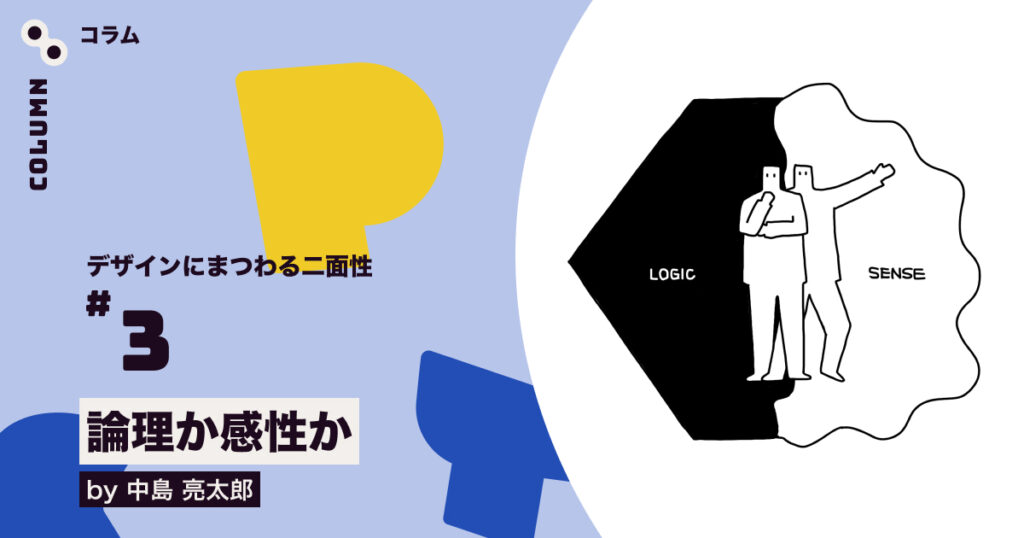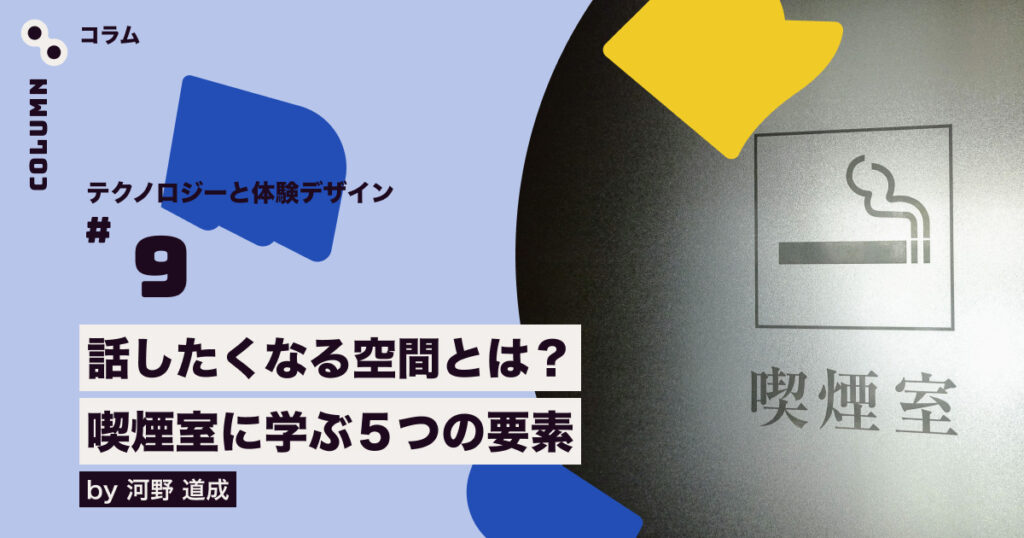日本のUXデザイナーが今でも思い出す、ロンドン芸術大学で学んだ10のこと
「学校で学んだことで、今でも役に立っていることはなんですか?」
パッと思いつくでしょうか。その時の教室の様子など思い浮かびますか? それとも時間をかけて少しずつ学んだことですか?
私は現在ustwo Tokyoでデジタルプロダクトデザイナーをしています。2018年9月から2019年6月まで、イギリスのロンドン芸術大学でインタラクションデザインを学びました。当時の英語力がクラスで下の方だったこともあり、授業についていくのがやっとでした。なんとかその場で理解できていたこともあれば、卒業後仕事に就いてから何年もかけてようやくわかりかけてきたこともあります。
この記事では、その学びを振り返りながら10項目にまとめます。各項目に関連する書籍もご紹介したいと思います。
1. 「ユーザー中心設計」は「ユーザーによる設計」ではない
“User-Centred Design” is NOT “User-designed”— 最初の授業で出てきたこのフレーズ。ユーザー中心を実践する中で常に心に留めている言葉です。
ユーザーを中心に置いてデザイン作業を進めることと、ユーザー自身がデザインを決めることは全く違います。インタビューでユーザーに「どれがいいですか?」と聞いて答えてもらったとしても、それが正しい答えだとは限りません。フォード・モーター・カンパニー創立者であるヘンリー・フォード氏の有名な言葉「もし、人々に”移動手段として何が欲しいのか?”と聞いていたら、彼らはもっと速い馬が欲しいと答えただろう」のように、ユーザーには何が必要か細かく見えてないケースがほとんどです。観察すること、その行動の裏の「なぜ」を引き出し、価値観や行動パターンを見出すことがユーザー中心設計の第一歩です。
『Don’t Make Me Think』by Steve Krug
初版が2000年に出ている本です。例もWebデザインが多く、一見古臭く感じるかも知れませんが、ユーザービリティにフォーカスしており、基本的な概念をシンプルに教えてくれます。ユーザーが「使いにくい」と言ったときに、「何が使いにくいのか」にすぐ気づけるための、必要な原則が書かれている本です。
日本語版:『超明快 Webユーザビリティ ユーザーに「考えさせない」デザインの法則』 スティーブ・クルーグ (著), 福田篤人 (翻訳)
2. 人はそれぞれ頭の中に地図を持っている
語学力が圧倒的に足りず、複雑な事が理解できなかった私は、入学当初ひたすらユーザーテストのやり方を覚えればいいと思っていました。ですが、その考えに待ったをかけてくれた出来事があります。
とあるデザインイベントで、登壇者が「UXデザインとは、ユーザーの地図で日陰になっているところにスポットライトを当ててあげることだ」という話をしていたのです。正直、イベント名も、登壇していたデザイナーさんの名前も覚えていないのですが、「地図にスポットライト」という表現がやたら印象に残り、今でもふとその時の壇上の光景を思い出します。
私たちは誰しも頭の中に「地図」と「マニュアル」のようなものを持っているのではないかと思います。地図はその人のこの世界の「認知」であり、マニュアルは人生を歩む中で育まれてきた価値観や、行動パターンです。そして、このシステムは感情や五感に左右される、少し頼りないものでもあります。
私はUXデザインの役割は、まずターゲットユーザーを観察することで「地図」と「マニュアル」をできるだけ深く理解し、次にその地図に沿ったデザインをしたり、時には日陰の部分にスポットを当て、最後にデザインの狙いが意図通りに機能しているかを検証すること、だと考えています。そのヒントをくれた、あの日登壇していたデザイナーさんの名前をいつか思い出したいのですが。
『The Design of Everyday Things』by Don Norman
認知学者であるD.A.ノーマンが書いた、改めて紹介するまでもない有名な本。日常のありふれた例が使われているので読みやすく、かつ読めば読むほど理解が進む本でもあります。認知科学の観点から人間がいかにメンタルモデルを形成するかが書かれており、人が人である以上ミスは必ず起こること、ユーザーが間違えるならそれはデザインの問題!という、デザイナーとしての基本の心構えを教えてくれました。
日本語版:『誰のためのデザイン?』D.Aノーマン (著), 岡本明 (翻訳), 安村通晃 (翻訳), 伊賀聡一郎 (翻訳), 野島久雄 (翻訳)
3. アウトプットだけが評価ではない
大学のコースはテーマ別にいくつかのモジュールに分かれていたのですが、各モジュールの流れは一貫していました。
- 座学で理論を学ぶ
- プロジェクトブリーフと、膨大な読書リストが渡される
- ブリーフに沿ってユーザー中心設計のアプローチでプロダクトを作る
- 結果をまとめて、全体のクラスでチームごとにプレゼン
- 1〜4の経験をもとに、アプローチと学びについてレポートを書く
作ったデザインの出来や、プレゼンだけが評価対象ではないのは目から鱗でした。つまり、プロジェクトで大失敗しても、そこから学んだことが大きければ十分いい成績を取れるということです。
バラバラな知識を持った人たちがチームを作り、それぞれの理解と意見を交換しながら、一緒に一つのものを作るというのは、デザインエージェンシーでアジャイルなプロジェクトに取り組む環境に似ています。できるだけ早く「ワンチーム」になり、お互いの能力と知識を活かし合いながら、モノづくりを進め、失敗を繰り返しながら学んだ事に一番の価値があります。どんなに自分一人で知識やスキルを高めても評価されず、高いレベルのコラボレーション力が試される環境は、その後のキャリアを作っていくための心構えを作ってくれました。
4. デジタルにすべきところと、すべきではないところを見極める
卒業論文で私が書いたテーマは「デジタルツールがアート制作のプロセスに与える影響」です。デジタルツールを避けがちな芸術家(画家などのファインアーティスト)と、デジタル・アナログのハイブリッドアートを作る芸術家の制作過程を追いながら、当時人気だったお絵描きiPhoneアプリ「Brushes」がアート制作に与える付加価値を理解しようとしました。

徹底的に自分の心に向き合うアーティストにとって「簡単には再現できない」、自分しか生み出せないその瞬間だけのものこそが価値です。簡単にコピペできてしまうデジタルツールはその正反対ですが、実はこの「再現できない」という要素がBrushesでも重要である事がわかりました。カラーピッカーが数値で入力できないなど、アナログで絵を描くように試行錯誤が必要なツールである一方で、「再現できないが故の試行錯誤の過程を記録し再現する」ための機能が備わっています。それをネットに公開することで、お互いに絵のテクニックを学びたいアーティストたちが物理空間を超えた、さながらアートカフェのようなオンラインコミュニティを作っていました。
敢えて面倒な体験を残しているBrushesは、必ずしも効率を上げることだけがいいデジタル体験ではなく、アナログ体験の中でもユーザーにとって価値があることは変えずに、デジタルはデジタルの得意な部分で価値を作ることが大切だと教えてくれました。
『The Language of New Media』by Lev Manovich
これも古い本で、芸術家であるマノビッチがメディア論として書いているので、必ずしもデザインに直結する本ではないかもしれません。しかし「デジタルらしさ」がいかに既存メディアに影響するのか綴られており、かつデジタル化の中にもアナログの不完全さ、不便さを取り込もうとする人間の不思議さを楽しめる本です。
日本語版:『ニューメディアの言語―― デジタル時代のアート、デザイン、映画』レフ・マノヴィッチ (著), 堀 潤之 (翻訳)
5. 形をデザインするのではなく、会話をデザインする
コースではUIデザインの方法自体にはあまり触れられませんでした。もちろんUIをデザインすることはありましたが、前項で書いたようにその出来などは採点の対象ではありません。また、フィジカルコンピューティングなど、必ずしもスクリーン上のUIのみだけではないプロジェクトもあったので、コースを通して常に「形じゃない何かをデザインしている」という感覚が強くありました。
数年後、会話型デザインという手法に出会い、ようやく腑に落ちました。システムを一人の人間だと捉え、二人の人間の間の会話をデザインするのだとすると、一番大切なのはお互いに「意味が通じる」ことです。情報アーキテクチャやインタラクションデザインというのは主にこの「意味付け(sense making)」をするプロセスであり、その上で「意味」を何で表すかはまた次のステップ。近年、アジャイル開発でチームのスピードがあがるとつい忘れがちなことですが、時間を使って意味を整える事には大きな価値があると思います。
『The Inmates Are Running the Asylum』by Alan Cooper
インタラクションデザインのツールとしてペルソナを世に広めたAlan Cooper氏。私がこの本が好きな理由は、コンピューターの「振る舞い」に焦点を置いていることです。UI/UXという表記が一般化されてきていますが、それだとどうしてもクラフト=形作りに気が取られてしまいがちです。UIだけではないその下レイヤーの中身が詰まったデザインをするために、「お行儀の良い」コンピューターの振る舞いを語るアランクーパー氏の本は定期的に読み返したくなります。
日本語訳:『コンピュータは、むずかしすぎて使えない!』アラン クーパー (著), Alan Cooper (原著), 山形 浩生 (翻訳)
6. 何事も自分で体験してみる
現在、ソフトウェアのUIといえばグラフィックベースのものが圧倒的に多いと思いますが、当然ながら音声ベースやハプティックなものなども存在します。アクセシビリティの観点からも、必ずしもひとつの手法に限ってしまわないデザインは重要です。…と頭でわかってはいるものの、では実際ユーザーはどのような「体験」をしているのか。その共感を本当の意味で持つには実際に体験してみる事が一番です。それを教えてくれたのは、校外学習でのとある体験でした。

blindekuh Switzerland / スイスにある暗闇レストラン
校外学習でのとある日、夕飯をこのレストランで頂きました。blindekuhは真っ暗闇の中で食事をするレストランです。スタッフはみなさん視覚障害のある方達で、入る時は電車ごっこのように前の人の方に掴まって進んでいきます。目隠しどころではない、目も慣れない真っ暗闇に入っていく恐怖感は言葉では表現できません。声だけを頼りに会話をし、手探りでフォークやナイフを見つけ、パンを食べグラスでワインを飲む体験は、視覚以外を使うインターフェースの感覚を味わわせてくれました。デザイナーとして一生記憶に残る体験だったと思います。
7. チームになるためにバックグラウンドは関係ない
コースに参加していたのはイギリス人だけではなく、20カ国からきた学生が集まっていました。自分も含め英語が第一外国語ではない人も多く、違う文化の中で教育を受けてきており、コミュニケーションの仕方も違う、価値観も違う。そういう人たちが、突然集められて「チーム」になるわけです。正直に言うと、ものすごく苦しみました。ただでさえ新しい事を学ぶ環境では話題の理解が浅いのに、言葉によるミスコミュニケーションが加わります。タスクを割り振ったはずなのに誰もやっていない、同じコンセプトを話していたはずなのに全く想像と違うものができてきたりなど、締め切り前はいつもカオス状態でした。
この環境に「日本人」気質全開で飛び込んだ私が真っ先に学んだのは、きちんと自分の意思を言葉にして伝えないといけないということ。空気を読んだり、表情で察してくれたりということは絶対にありません。先入観なしに相手の話を聞き、例え多少空気が悪くなろうとも、反対意見もきちんと口にしないといけない。チーム全体でコミュニケーションをしっかりとっていかないと、後から問題が吹き出てきて、結果が散々になってしまいます。
今考えるとこれもエージェンシーの環境に似ています。苦しみましたが、学生の頃にこういった環境への心構えができたのは価値のあることでした。多様性のあるチームは難しい。信頼関係を作って、お互いの良いところを活かせるようになるまでに時間がかかります。それでも不可能ではないし、機能し始めた時の楽しさは格別です。(……という事が心から実感できたのは、今の会社に入ってからです。)
8. ひとつ共通の概念図があると話が進みやすい
多様なバックグラウンドの人たちが集まった時にまず取り組むべきなのは、なるべく早く「共通言語」を打ち立てることです。これがあると話がしやすいし、意見の相違や、ミスコミュニケーションがあったときに、どこが合っていないのかを理解しやすい。システムとユーザーとの関係性と同じで、共通のメンタルモデルを作るようなものです。
コースの中で渡された膨大な読書リストの中で、「必読書」に指定されていたいくつかの本、前述のDon’t Make Me Think(超明快 Webユーザビリティ)やDesign of Everyday Thing(誰のためのデザイン?)は、まだまだ未熟な学生デザイナーたちがかろうじてチームとして機能するための共通理解として役に立ってくれました。
『The Elements of User Experience』by Jesse James Garrett
UXデザインやデザイン思考などの分野には数えきれないほどの概念図があります。それぞれ違う視点から表現しているので、どれが一番正しいといった議論は不可能です。その中で私が一番「使いやすい」と感じているのが、このThe Five Elements of UX(UXデザインの5段階モデル)。これもWebデザインを前提にしたクラシックな本ですが、戦略という抽象的な概念から、表層レイヤーで具体的なUIになるまで「意図が変換されていく」と考えると、プロジェクトの各フェーズでのフォーカスが見つかりやすくなります。シンプルな概念かつ、作業の流れにも沿っているという点で、馴染みやすいフレームワークだと思います。
日本語訳:『The Elements of User Experience 5段階モデルで考えるUXデザイン』ジェシー・ジェームズ・ギャレット (著), ソシオメディア株式会社 (翻訳), 上野 学 (翻訳), 篠原 稔和 (翻訳)
9. ビジネスとはお金だけのことではない
イギリスで学生をやってみて新鮮に感じたことの一つが、起業を応援する文化でした。現役のデザインエージェンシーからゲスト講師を呼び、ビジネスモデルを考えるプロジェクトがあったり、学生が無料で受講できるサマーコースにはスタートアップについて学ぶものもありました。デザイナー志望でもアーティスト志望でも、卒業後就職するのではなく自分でビジネスを始める事を考えている人が多かったのも印象的です。学生でもエンジェル投資家が時間を取って話を聞いてくれたり、社会全体として起業を進める文化があったように思います。
実は当時私はこのビジネスに関する授業に興味が湧かず、あまり詳細を覚えていません。「デザイナーなんだし、作ることにしか興味ない」「お金の話は苦手」「いつでもユーザー側にいたい」と考えていたからですが、これは実際にエージェンシーに入ってからかなり後悔しました。もちろんユーザーの声をビジネス側に届けるのは大事です。しかし、サービスやプロダクトを提供するのには持続可能なビジネスモデルが必要であり、デザインはそれも理解した上でユーザーへ価値を届けなくてはなりません。まったく当たり前のことですが、学生の私はそれがわかっていませんでした。
『Rework』by Jason Fried & David Heinemeier Hansson
basecampで有名な37Signalsの本。卒業してすぐ、友人に誘われてこの本のローンチイベントに参加することになり、お土産としてもらいました。読まずにずっと放置していたのですが、実際に現場で働くようになってから読み返してみると面白い!個人でビジネスをやっている人たち、スタートアップ企業のためのマインドセットが書かれています。 私がビジネスモデルのクラスに興味が持てなかった理由は、ビジネスとは「何かを売って利益を出す」だけの話だと思っていたからです。しかし、この本を読むと、ビジネスとは必ずしもお金のことだけではなく、文化、コミュニティ作りや働き方、毎日の生き方の話であるということがわかります。起業などを考えていない人でも一読の価値がある本だと思います。
日本語訳:『小さなチーム、大きな仕事』デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン (著), 黒沢 健二 (翻訳), 松永 肇一 (翻訳), 美谷 広海 (翻訳), 祐佳 ヤング (翻訳)
10. わからないことはわからなくてもよい
さて、膨大な読書リストの中で、手に取ってみたものの、1ミリも理解できずに挫折した本があります。
『Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid』by Douglas R. Hofstadter
日本語訳:『ゲーデル、エッシャー、バッハ』ダグラス・R. ホフスタッター著
当時の自分の英語力では1ページも理解できなかったこの本。クラスメートが読んでものすごく面白かった、と言っていたのが悔しくて、実はハードコピーを買って日本に持って帰ってきています。そして、いまだにパラパラ数ページめくっては挫折感を味わっています。これが枕にできそうなほどの分厚さ。
1年間イギリスの大学に行った中で、「何が何だかさっぱりわからない」瞬間がたくさんありました。クラスメートより本を読むスピードも遅く、会話についていけない、先生が言わんとしている事がわからない、チームメイトに何を頼まれたのかわからない、他のチームのプレゼンの後のディスカッションについていけない。1年間を振り返ると必死さと悔しさの塊、としか表現できません。
ですが、エージェンシーで働くデザイナーになってみて思うのは、知識やフレームワークの移り変わりが激しいデジタル業界では、「完璧に知識をマスターした」瞬間など訪れることはなく、学び続ける姿勢の方が大事だということです。悔しさは次の頑張りへの力になりますが、その時わからなくてもまた学べばいい、勉強すればいい。あまり気にしすぎないことです。この本はその時の悔しい思いの象徴であり、学ぶ姿勢をやめないためのリマインダーでもあります。
今わからないことは、わからない。いつかわかるようになるかも。もしみなさんがこの本を読んだ事があっても、私に説明しようとしないでください。いつか自分で楽しめるようになるように頑張っているところなので。